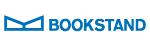がん、認知症、糖尿病、うつ病――あらゆる病や不調に取り入れたい生活習慣のコツ

追いきれないほど多くの情報が飛び交っている現代。自身の健康のために「何を選べばいいのか」「何を信じればいいのか」と、迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。そんなときに、皆さんの道しるべとなってくれるかもしれないのが、書籍『小さな町の精神科の名医が教える メンタルを強くする生活習慣』。鳥取県米子市で地域に根差した精神科医として数多くの患者を診てきた飯塚 浩氏が、「心と体を支える循環」を回復させる生活習慣について記した一冊です。
戦後80年の間に、日本ではがんや認知症、糖尿病、うつ病といった慢性疾患とメンタル不調がかつてない速度で広がっています。これは食生活、働き方、人間関係、価値観が一気に変質したことで、私たちの体とこころの循環システムが同時多発的に崩れたからというのが著者の考え。「健康とは循環である」という視座を持ち、本来の良い循環を取り戻すことが大切であると説きます。
中でも非常に重要となるのが「食事」です。たとえば、日本では戦後、小麦の摂取量が激増しましたが、日本人のように小麦食の歴史が浅い民族は、花粉症やアトピー性皮膚炎、炎症性腸疾患などの幅広い不調がより表面化しやすいことが近年明らかになってきたそうです。これらの疾患の対策として効果的なのは「火種を断つ」、つまりグルテンフリーを徹底すること。小麦粉を控える程度ではなく完全に除去することで初めて、炎症ループのスイッチを切ることができるといいます。本書では小麦のほかに乳製品、植物油、精製糖についても、それらがいかに日本人の体質とはミスマッチであり、慢性炎症や免疫の乱れを引き起こしているか解説しています。
いっぽうで、循環を育む食事として著者が勧めるのが、日本列島で長く受け継がれてきた「風土食」。「主食は米と雑穀を中心に」「発酵食品を毎食取り入れる」などの7つの原則を頭に置くだけで、シンプルかつ満足度の高い食事に変わることが期待できます。本書では1日のモデル献立や定番レシピなども紹介されており、風土食に馴染みがない人も取り入れやすいかと思います。著者によると、「風土に根差した食材と発酵文化を取り戻すことは、単なる個人の健康を超え、社会システムの健全化につながる行動です」(本書より)とのこと。食に関する選択と行動が、私たちの健康だけでなく未来にもよい循環をおよぼすと言えそうです。
本書では、「1、風土食を再興する」「2、加工食品を適切に制限する」「3、自然と食の循環を共有するコミュニティを育む」という3本柱で、がんや認知症、糖尿病、うつ病といった慢性疾患の真因を解き明かしています。”生涯折れないメンタル”を支える基盤を手に入れたい方は、試しに読んでみてはいかがでしょうか。
[文・鷺ノ宮やよい]
- ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
- 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。