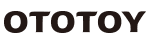スタジオと音楽の麗しき共犯を追えーー高橋健太郎著『スタジオの音が聴こえる』を紹介しよう

音楽評論家、音楽プロデューサー、レコーディング・エンジニア、そしてOTOTOYのプロデューサーでもある高橋健太郎。
『スタジオの音が聴こえる 名盤を生んだスタジオ、コンソール&エンジニア』は、ひさびさ(実に24年ぶり)の刊行となる氏の単著である。
現在、OTOTOYでもおなじみのハイレゾを中心とした、氏の音楽にまつわるレコーディング・テクノロジーの追求、その起点が垣間見れる書籍でもある。
本書は『ステレオサウンド』での2009年からの連載の書籍化である(連載にはなかった書籍のための書き下ろしも1編)。その内容とはずばり、さまざまな名盤が生まれたスタジオたちについての物語だ。
取り上げられているのは、1960年代から1970年代に建造されたスタジオが中心(一部1980年代、1990年代も)。ローリング・ストーンズ、ジミヘンなどロックの伝説的名盤を数々生み出した〈オリンピック・スタジオ〉、カーペンターズやジョニ・ミッチェル、ミニー・リパートンなど女性ヴォーカルものの名作を多く残す〈A&Mレコーディング・スタジオ〉、サザン・ソウルの〈フェイム・レコーディング・スタジオ〉、さらにはディスコの発信源、フィリー・ソウルの〈シグマ・サウンド・スタジオ〉、ロック、ポップスはもちろんスラロビ&スティーヴン・スタンレーの布陣でレゲエからガラージュ・クラシックも発信した〈コンパス・ポイント・サウンド〉、クラフトワークなどクラウト・ロックの震源地として、さらにはニューウェイヴなどを多く手がけたコニー・プランクのスタジオ、そして本書の例外中の例外、1990年代設立、シカゴ音響派〜ポストロックの牙城、ジョン・マッケンタイアの〈SOMA〉まで多岐にわたる。
端的に言ってしまえば、上記にあげたアーティストたちが残した、20世紀のポピュラー・ミュージックの名作の数々をスタジオ、つまるところコンソールをはじめとしたレコーディング機材、セッティング、そしてレコーディング・エンジニアの手法などを軸に解析しているのだ。
こう書いてしまうと、少々テクニカルな解説のように、とっつきにくい印象を持つが、そんなことはない。自分のようなレコーディング機材に無頓着なものでも理解しやすい。まるで物語のように、各スタジオからレコードへと封じ込まれた音楽的なプロセスが描かれている(僕のような人間はぜひ巻末から読もう!)。もちろん、その手の職業人たちとしてはその情報の価値は天井知らずといったところだろう。
本書を読むと、まずはそこに書かれている名盤たちを引っ張り出し、もう一度確かめてみたい衝動にとらわれる(YouTubeじゃわからん)。もしくは未聴のものも、その記述が気になればどうしても聴きたくなる。新たな作品への興味を生む、それだけでも音楽好き冥利につきる。だが、さらに本書の視座を通して聴くと、これまで音楽を聴く上であまり気にしていなかった部分に気づくことになる。それはある種のテクノロジーやエンジニアの手腕といったものの差異が、確実に耳に聴こえるものとしてそこに情報として残されていることだ。
その気づきの下に、音楽を追っていくと、さらに新たに、ポピュラー音楽の歴史への認識が変わっていく。なんだか20世紀のポピュラー・ミュージックの爆発的な進化の一端は、天才的なアーティストのひらめきだけでなく、こうしたテクノロジー、もちろん、そこには名エンジニアの手腕といった人的なテクニックも含めて録音芸術としてのあり方が大きく担っていたのではないかということだ。それを文字通り肌で感じることができるだろう。
21世紀はどうだろうか? もはやこうした”スタジオの力”というべきものは、実は音楽の進化に大きく力を及ぼしていることが証明され、さらに身をもって感じることができる世紀になった。本書でも語られるように、PCを中心としたDAWのシステムはここに出てくるスタジオのテクノロジーやエンジニアたちの英知をデジタルの形で凝縮したものと言えるだろう。いまやレコーディングの中心はほとんどが、このシステムの上にあると言っていい。そして、局所的なところを例にとっても、このDAWのシステムの進化は、エレクトロニカを誕生させ、サウンドシステムを極限まで刺激的な音で”鳴らす”ベース・ミュージックやEDMを生み出していると言える。つまりは、もはや最新のジャンルやシーンすら作り出している。
少し話は戻るがダブやポストロックは、こうしたテクノロジーとしてのスタジオの存在を演奏や作曲と同等の楽曲制作にまで拡大解釈したわけだが、こうした手法以前に、すでに音楽が録音製品となった時点で、そうしたスタジオというテクノロジーの具現物やエンジニアの手腕がサウンドを支配し、音楽そのものに影響を及ぼしていたことがわかる。そんな著書だ。
「1972年のレコードはなぜ音がいいのか?」という著者の疑問(本書のライナーノーツともいえる「Output」をぜひとも)からはじまった本書の思索と調査の旅は、最先端のテクノロジーと音楽の進化の共犯関係とも共鳴するものでもあるのだ。なんとなくだが、氏のハイレゾ、DSDへの追求もこうした視座の上ならば、当然のことではないかと腑に落ちてしまう。
取り上げられているスタジオ、目次など詳細は下記、版元のDU BOOKSのホームページにて。オーディオ評論家の和田博巳、アーティスト / プロデューサーの冨田ラボこと冨田恵一を迎えた、出版記念のトークイベントも開催予定(詳細は下記にて)。
(河村)
・高橋健太郎著『スタジオの音が聴こえる』〈DU BOOKS〉
http://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK109
アナログ録音の真髄を聴く!~レコードから聴こえるスタジオの音、エンジニアの音とは ? 」
6月26日(金)19時
@dues 新宿
ゲスト:和田博巳
録音芸術は総合芸術だ! スタジオの音を聴く」
7月4日(土)15:00 ~
@diskunion JazzTOKYO(御茶ノ水)
ゲスト:冨田ラボ
- ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
- 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。