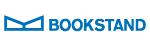なぜ人間だけが「性」に振り回されるのか ”進化生物学”から読み解く人間の「愛」

社会的価値とされる「信頼」や「協力」もまた、進化上の利害から生まれた振る舞いなのかもしれない。見えにくい仕組みのなかに、人間ならではの行動が自然と織り込まれているように思える。
また、本書で印象的だったのが、「男はなんの役に立つのか?」という問いかけである。この挑発的な表現は、家族のかたちや夫婦の関係、子どもを育てていく過程での役割など、さまざまな観点から男性の存在やふるまいがどのような意味を持つのかを考えさせられる。
オスが大型動物の狩りを担い、メスが植物採集と育児を担当する。この役割分担は、現代の社会にもかすかに痕跡を残している。表向きには”家族の利益を高める健全な協力”とされているこの構造も、実はもっと複雑な戦略を抱えているようだ。
そもそも、狩りは必ずしも安定した栄養供給源とは言いがたい。獲物が手に入る日より、手ぶらで帰る日が多いからだ。それにもかかわらず、男性は堅実な採集には加わらず、リスクの高い狩りへと向かっていく。この行動の背景には、家族の利益とは別の思惑が潜んでいる可能性があると、著者は疑っている。
「男の狩りに気高い動機を見ようとして見逃しているなんらかの卑しい動機があるに違いない」(本書より)
この指摘には、生々しいリアリティがある。著者は、家族に安定的な食料を供給する「扶養型」と、危険を伴いながら名声を得る「誇示型」という二つの行動パターンを対比させながら、オスの内面に潜む本音を探っている。
「誇示型」の男性は、大型の獲物を仕留め、部族に分け与えることで高く評価される。その結果、妻以外の女性から性的な関心を集める機会が生まれ、女性側も一時的な関係を通して栄養の恩恵を得ることがある。
こうして見ると、「誇示型」の行動はただの”狩り”ではなく、社会的な評価や性的な機会を得ることによって、自身の遺伝子を広げようとする複合的な戦略になっている。著者はこの進化的な本音を浮き彫りにすることで、女性にとって「扶養型」の男性が魅力的であっても、男性自身にとっては必ずしもそれが望ましい選択ではないという現実を明らかにしている。
性の振る舞いに進化の力が働いていることを知ると、人間関係の見え方が少し変わってくる。本書は、そんな”当たり前”の裏側に目を向けるきっかけとなるだろう。
- ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
- 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。