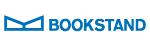“ただ普通でありたかった”男の人生〜月村了衛『普通の底』

2025年の現実を犯罪小説的視点で見ればこういう長編になる。
先般、『虚の伽藍』(新潮社)が高校生直木賞に選ばれたばかりの月村了衛が、書き下ろし長篇『普通の底』(講談社)を上梓した。正確に言えば、「小説現代」に一挙掲載されてからの刊行である。版元が期待を寄せていることがよくわかる。先月『おぼろ迷宮』を取り上げたばかりだが、別傾向の作品だし、これを紹介しないわけにはいかない。
本書は「第一の手紙」「第二の手紙」「第三の手紙」の三章で主部が構成されており、その後に付章があって完結という構成になっている。付章の題名はここでは伏せておこう。手紙とあるが、告白手記の体裁である。「ただ普通でありたかった」「本当にそれだけなんです。他にはなんにもない。本当です」という二文から「第一の手紙」は始まる。思いがけず自分の人生について振り返る機会を与えられた書き手が、その相手に向けて語りかける形で文章は進んでいく。書き手はこの手記を、いつもSNSで使っているような短い言葉の羅列や、友達同士の会話とは違う「ちゃんとした文章の言葉」で書くつもりだと言う。
どうということのない文章だが、実はこれは決意表明である。「ちゃんとした文章の言葉」で自らを振り返ることがなかった人生だったのだ。初めて自分自身と対峙した書き手は、ふさわしいやり方があるということに気づいた。「ちゃんとした文章の言葉」で考えることがない人生とはどういうものか。そのモデルが以降の物語では示されることになるだろう。
語り手は二〇〇一年生まれで、川辺優人という名前である。彼が、二〇二五年の現在に向けて歩んでいく人生を描くことが本作の眼目だ。
優人という名前は、父の義昭は「義春とか義正といった名前を考えていた」が母の絵美子が「古い、昭和感まる出し」と嫌がって強引に決めた。絵美子は「どんなことでも自分の意見を押し通そうとする人」で、義昭が「反論を試み」ても「全部言い終わらないうちに母が強い言葉で主張を繰り返」すため、折れざるをえなくなってしまう。二人は職場結婚で、そういう場合は女性のほうが辞めるべきであるという同調圧力に負けて絵美子は退社をしたという過去がある。そのため絵美子は、会社に残っていたら自分のほうが義昭より出世していたはずだという意味のことを、夫の前で言ってしまうこともある。
現在でも男性優位の傾向は社会に根強いが、昭和から平成にかけての時代にはさらに色濃かった。優人の語りは時折このように、彼が個人史、あるいはその前段階としての家族史として振り返る時代がどのような背景、そして精神的基盤の上に成り立っていたかについて言及するのである。優人は、自分は決して特別な高望みをしていたわけではないと言う。「第一の手紙」冒頭に書いたように「ただ普通でありたかった」だけだからだ。したがって彼が語る時代風景とは、優人の目から見た普通なのである。
そこに違和感を持たれる読者も出るだろう。優人という人間に感情移入できないと思うかもしれない。そのときは語りを拒絶する前に、主人公と自分の間にどのような隔たりがあるのか、と考えてみていただきたい。逆に優人は自分自身だと胸に刺さる人もいるだろう。その場合は、なぜそう感じたかに思いを馳せてみていただきたい。
そのときどきの時代背景が描かれているという以外に、両親を巡る短い挿話からもう一つわかることがある。優人がどのような人に囲まれて生きてきたか、ということだ。母と父の関係に関する叙述は、読者に不安な感情をもたらすはずだ。危なっかしいものを感じさせる記述だからである。後に続くエピソードでは案の定、両親の間に不和の種が育ち、亀裂が走ることになる。優人はそれに目を背けながら生きていくことになるのだ。この消極的な現実否認が彼の人格に影響を及ぼすことになる。主人公を巡る人間関係が、その人生がどう展開するかを大きく左右するのである。これは典型的な性格劇の作法だ。注目すべきは、主人公を含む登場人物たちがどのような性格・性質として描かれているかということなのである。
親ガチャ、という言葉がある。『普通の底』で書かれているのは、子の人生は親の出自次第である、というような単純な決定論ではない。客観的に見れば川辺家は中流階級に属している。優人は大学進学に当たって奨学金を利用することになるが、それは貧困のためというより、両親が別居状態に陥ったことにより、学資の余裕がなくなるからだ。直接の引き金は父・義昭が地方支社に飛ばされ、単身赴任を選択したことである。その原因は義昭がパワハラだと訴えられたことで、優人はそれを聞いて「正直ありそうだな」と考える。
優人の記述には自分しか存在せず、他人の感情も、彼がそう考えたというフィルターを通じてしか描かれない。つまり、ここで描かれる両親の姿も彼の目に映ったそれである。学校の内外で出会う同世代の人間に対しても、同じような視線が描かれる。優人が何を考えているかは、実は記述を見てもよくわからない。上に書いたように、過去の彼には「ちゃんとした文章の言葉」で考える習慣がないからだ。代わりにわかるのは、周囲の人にどのような視線を向けるかということである。
小学校の同じクラスには菊地というボスがいたが、彼は中学受験に失敗して一気に地位を喪う。中高一貫の私立に進んだ優人は、菊地のいる公立校に行かなくてよかったと胸を撫でおろす。高校三年生のとき、クラス委員の高井戸に連れられて新宿に遊びにいき、ケーシンと呼ばれる男と知り合う。ケーシンはいわゆるトー横の顔役で、未成年女子を騙して集団的な性犯罪を行っている。優人はそれに巻き込まれそうになり、危ないところで逃げ出すことに成功する。
危ないところでいつも優人は危機から免れる。犯罪小説的展開を予想して読んでいると、そのたびに肩透かしをされるだろう。だがそれは、いつまでも逃げてばかりだということでもある。自分が巻き込まれた事態に向き合おうとする態度は、優人から最も遠いものだ。自分と面識がある人間が犯罪に関わったことを優人は悪罵する。他人事であり、すべて自分とは関係ないことだと切り捨てる。
そうした性格、社会との向き合い方の人物が主人公なのである。犯罪小説とは、個人と社会との根本的な対立関係を描くものだ。優人にとって社会は、自分を虐げる理不尽な重石や枷のように見える。その中で他の人と同じ「普通」の生き方をするということが彼の目的である。果たしてそれは成功するのであろうか。優人の見ている社会には、自分と同じ価値を認められるような人間は存在しないはずである。何しろ彼にとって他人とは、自分にとっての脅威なのだから。そんな人間の普通とは何かと物語は問いかける。
物語が典型的な犯罪小説展開になるのは「第三の手紙」章がだいぶ進行してからなので、すべて省略して紹介してみた。題材とされる出来事はみな記憶に新しいので、そうした事件に取材した小説と感じられるかもしれない。だが、そうした部分は皮相であり、小説の本質は優人というキャラクターの中にこそある。読み終えたらもう一度考えてもらいたい。優人はあなたなのか。あなたではないのか。あなたとはどこが同じなのか。何が違うのか。あなたはいったい誰なのか。
(杉江松恋)
- ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
- 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。