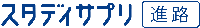テスト時に役立つ!復習しやすい授業中のノートの取り方とは

学校で毎回ノートを取っているけど、ただ黒板を書き写しているだけで、本当に内容が頭に入っているのかわからない…という人も多いのでは?
カラーペンやマーカーペンは何色まで使っていいの?授業中の先生の話もノートに書いたほうがいいの?などのちょっとした悩みから、勉強に使える!しっかり頭に入るノートの取り方まで、みんなのギモンとともに解決していくよ!
今回教えてくれたのは、小学生から東大合格生まで、たくさんの生徒や学生たちのノートを取材して、数多くのノートについて執筆している太田あやさん。
【今回教えてくれたのは…】
太田あやさん
石川県出身のフリーライター。
小学生~高校生向け通信教育講座の編集を経て、フリーライターに転身。
以後は教育分野を中心に執筆活動を行っている。
キャンパスノート(ドット入り罫線)を株式会社KOKUYOと共同開発。
著書に『東大合格生のノートはかならず美しい』『東大合格生のノートはどうして美しいのか』『東大合格生の秘密の「勝負ノート」』(以上、文藝春秋)、『マンガでわかる! 頭を鍛える 東大ノート術』(宝島社)、『非進学校出身東大生が高校時代にしてたこと』(小学館)など多数。
そもそも何で授業中にノートを取るの?必要なの?

※授業の復習やテスト対策の為に授業中にノートを取ることは重要!
授業の復習をして自主学習に活用する
「授業中にノートを取ることは、とても大事で、必要なことです。黒板の内容だけでなく、先生の解説を聞いて補足をしたり、覚えておくべきだと思ったことや疑問点なども書いておくことで、授業の復習やテスト勉強にも使えます。
ノートの取り方に正解はなく、自分の目的を達成するために、自分にとって一番やりやすい方法で、ノートを取ることが肝心です。
では、実際にどんなことに気をつければいいのか、みんなのギモンに答えていきましょう」
(太田さん)
授業中のノートの取り方

※いかに簡潔に見やすく書くかがポイント!
授業ノートは黒板・解説・自分が思ったことを書く
【授業中のノートの取り方について、みんなのギモン】
・「授業中はノートを取ることに時間をかけたほうがいいのか、簡潔に書いたほうがいいのか」(高3男子・富山)
・「授業中は先生に言われたことを自分が読める程度の汚い字でとりあえずぐちゃぐちゃに書いて、家に帰ってからきれいに書き直すのは効率が悪いですか?」(高3女子・大阪)
・「授業ノート以外に、自主学習でもう一度ノートをまとめる必要があるのか」(高1女子・岐阜)
「授業ノートには、黒板の内容・先生の解説・自分が感じたことや疑問点の3つを書きましょう。箇条書きで、いかに簡潔に書くかがポイント。
必ず家で見直しをして、知識を追加したり、間違えた問題の内容を書いたりして、授業ノートを育てながら、まとめノートにしていくのがベストです。家で一から書き直して、もう一度まとめ直すのは、時間がもったいないので避けたいですね。
ただし、読めない字だけを、まだ授業の記憶が残っているうちに書き直したり、付け足したりすることにはすごく意味があります。
それを見直しと一緒にやっておくと、授業の内容を思い出すことができて記憶の定着が図れます。
高校生になると科目数も学ぶ範囲も広くなり、授業ノートとは別にまとめノートを作り直すのは大変なので、いかに授業ノートをテスト勉強にも使えるようにするかが重要。そこを意識しながら、授業中にノートを取るといいと思います」
(太田さん)
先生の発言や自分が疑問に思ったことを優先的に書く
【授業中のノートの取り方について、みんなのギモン】
・「板書のものを書くべきか、先生の発言したこと(板書には書いていないこと)を優先的に書くべきか」(高2女子・東京)
「両方とも大事ですが、どちらかと言えば、先生の発言を優先してほしいですね。黒板の内容は、黒板が消されるまで残っているし、友達のノートを見せてもらうこともできますが、先生の発言や、そのとき自分が疑問に思ったことは、その場でしか書けません。
そこにこそ、自分のノートのオリジナリティーや、授業内容を理解したり、記憶するためのきっかけになるものがつまっています。
基本は、先生の発言、そのとき自分が疑問に思ったことを優先的に書くといいでしょう。人それぞれ、ひっかかるところは違うし、なるほどと思うことも変わってくるはず。
そこを大事にしていくと、授業の受け方も受動的ではなく主体的になります。黒板を写す時間がなければ、ノートにラインを1本引いて板書分のスペースを残しておき、休み時間に書いたり、友達に見せてもらえばいいと思います」
(太田さん)
授業ノートを書く目的とルールを決めよう
【授業中のノートの取り方について、みんなのギモン】
・「数学のノートに、教科書や青チャートに書いてあることを写すのは意味がある? 例えば英語のノートで、〇〇は絶対に書いておけ、ということはある?」(高1男子・愛知)
「教科書や参考書の丸写しは意味がないと思います。ただ、理解が浅い部分、覚えなくてはいけない部分、間違えた箇所などを選んで書くことは、すごくいいことだし、ぜひ書いてほしいと思います。ノートに対し、目的意識がないと、何を書いたらいいのかわからなくなると思います。
例えば、その英語のノートでは何を学んでいて、学んだことがテストでどう問われるのか、それとも課題提出用のノートなのか、それによって書く内容が違ってくるので、ノートの目的を明確にして、必要なことを書いていくのがいいでしょう。
先生に『ここはテストに出るからノートに書きなさい』と言われて、受け身でノートを取ってきた人も多いと思いますが、ノートは主体的に書いていかないと、勉強に役立つノートにはなりません。ノートには、自分が必要だと思ったことは何を書いてもいいのです。
まず、自分でノートを書く目的を決めて、ルールを決めましょう。もちろん、すぐにはできないと思うので、試行錯誤をしながら、自分に合ったノートの書き方をみつけていってほしいですね。
友達のノートを見せてもらったり、ノートアプリやSNSなども参考にして、いろいろなノートを見てみるといいでしょう」
(太田さん)
★Real Voice:「授業中にノートを取るとき気をつけていることは?」★
・「板書の内容だけでなく、自分が気づいたコツや覚え方もプラスして書いている」(高1男子・長野)
・「ノートの右側にスペースを開けて、先生が言ったことをメモする」(高3女子・北海道)
・「教科書に書いてあることはノートに書く必要がなく、手間になるので書かない。その分、先生が大事だと言ったところや自分がわかりにくいと感じたところはしっかりメモを取る」(高1女子・愛知)
・「教科書の太文字の語句の意味を書くようにしている」(高2女子・北海道)
・「先生が黒板に書かないことでも、大事だと思ったことはメモする。わかりきっていることはあえて書かず、知らなかったことのみ書いて、わからないところを明確にする」(高2女子・兵庫)
・「パッと見で振り返りやすいノートではなく、授業で聞いたことを全部詰め込む。振り返るには全部をじっくり見ないといけないので、自然と授業を思い出す」(高1男子・愛知)
・「黒板に書いていないことも書く。自分なりに言葉を変えて、あとから分かりやすくしている」(高2女子・三重)
テスト対策にも使える!勉強に役立つノートの取り方

※家で復習するときに見やすいノートってどんなノート?
一言メモで読み返したくなるノートに
【勉強に役立つノートの取り方について、みんなのギモン】
・「やる気が出ないときでも、あとで見返したくなるようなノートの取り方が知りたい」(高1女子・愛知)
「一言メモを入れてみてはどうでしょう。その授業のときの気分、先生の服装でもいいので、日記感覚で何かメモしたり、コメントを入れておくと、見直すときにおもしろくなると思います。
例えば、先生があの服を着ていたときに、こんな話をしていたな、などど、授業内容や暗記したことをテストのときに思い出すヒントになるかもしれませんよ」
(太田さん)
ポイントになる部分を目立たせる
【勉強に役立つノートの取り方について、みんなのギモン】
・「書きながら覚えられるようなノートの取り方を知りたい」(高1女子・東京)
・「あとから暗記をする場合、どのようなノートの書き方がいいのか」(高3男子・奈良)
「1回書いただけで覚えられる人は少ないと思うので、覚えなくてはいけないことを目立たせるようなノートの書き方を工夫しましょう。覚えるべきところに☆マーク入れる、赤字で書いておくなど、目立たせる書き方をしておくと、印象に残るし、覚えやすくなります。小さな丸いシールや細い付箋を貼ってもいいですね。
家で見直しをするときに、これは先生の話、友達の話、覚えるところなどと色分けして小さな丸いシールを貼って整理する人もいますよ。
暗記の勉強に使いたいなら、暗記すべき部分を赤シートで隠せる色で書くといいでしょう」
(太田さん)
授業ノートを見直して育てていく
【勉強に役立つノートの取り方について、みんなのギモン】
・「テスト勉強をするための事前準備になるノートの取り方を教えてほしい」(高2男子・島根)
「授業ノートを充実させること。例えば、定期テスト対策なら、この授業ノートを書くことで、テスト勉強にどう使いたいか、ノートを取る目的を決めましょう。
定期テストの目標点を決めて、その点を取るために、授業ノートをどう書こうか。書いたら毎日見直す習慣をつけ、どんどん書き込みをして、授業ノートを育てていく。
テスト期間になったら、問題集などをやって、できなかった問題、覚えられていないことなど、追加の知識を授業ノートに書き足していきましょう。それを見直しすることで、効率良くテスト勉強ができると思います。
定期テストが終わるたびに、勉強法の見直しもするといいですね。目標点数が達成されれば、その勉強法はOKだったと考えていいけど、目標点が取れなかった場合に、何が悪かったか、何が足りなかったか、じゃあ、ノートはどう書けばいいのかを考えて、試行錯誤していく。
自分に合ったノートの取り方は、自分でみつけるしかないので、あきらめずにやっていってほしいと思います」
(太田さん)
あとから見直しても理解できる!見やすいノートを書くコツを知りたい!

※授業中のノートの取り方は、キーワードやポイントを書くことが大事!
書き出しを早くしてキーワードで書く
【見やすいノートの取り方について、みんなのギモン】
・「授業中に遅れずテキパキと、板書を写したり、先生が言ったことをメモするコツを知りたい」(高1女子・福岡)
「まず書き出しを早くすること。黒板がある程度、完成するまで待っている人は少なくありませんが、そこまで進んでから書き始めると、先生の解説も始まってしまって間に合いません。
先生と同時に書くくらいのつもりで書かないと、黒板を写すのに熱中して先生の解説が聞けなくなったり、先生の解説をメモできなくなるので、書き出しを早くしましょう。字が少しくらい乱れても気にせず、見直したときに自分のテンションが下がらないレベルで、なんとか読める字でいいのです。
先生の話をすばやくメモするコツは、キーワードで書くこと。その言葉があればあとから先生の話が思い出せるようなキーワードになる単語だけ、関連している内容の近くに書くといいでしょう。大切なのは、授業ノートをその日のうちに見直す習慣をつけておくこと。
キーワードしか書いていなくても、記憶が浅いうちなら付け足すことができます。授業ノートは、授業中で完結させるのではなく、あとから授業で書いたものを見直して、より良くしていくつもりで書くと、授業中に不安なくノートを取ることができると思います」
(太田さん)
あとから書き足すスペースを空けておく
【見やすいノートの取り方について、みんなのギモン】
・「あとから書きたいことが増えたけど、書くスペースがない場合はどうすればよいのか。別の紙だとなくしてしまうし、ギュウギュウに詰めても読みづらくなってしまう」(高2女子・千葉)
・「詰めて書いて1ページにたくさんの情報を入れるのか、空間を空けて見やすくするのか、どちらがいいのか」(高1女子・東京)
・「楽に継続できるようなノートのきれいな整理のしかた、付箋の使い方を教えてもらいたい」(高2女子・福岡)
「あとから知識を追加できるスペースを考えて、余白を取りながら書くようにしましょう。付箋やルーズリーフなどをノートに貼り足してもいいですね。
どうしても、うまくスペースを取って書けないなら、ノートのサイズを大きくするという方法もあります。授業ノートは、余白があったほうが見やすくなるし、見直しもしやすいのですが、例えば、単語や漢字などを覚えるためのノートなら余白は必要ありません。」
(太田さん)
文頭をそろえる、ラインを引いて仕切る
【見やすいノートの取り方について、みんなのギモン】
・「どうすればきれいなレイアウトで書けるのか、簡潔にまとめるにはどうすればよいのか」(高1男子・埼玉)
・「書いていることがぐちゃぐちゃになってしまうことがあるが、見やすくノートを取るためのコツはあるのか」(高3女子・北海道)
「きれいなレイアウトで書くコツは、
1)文頭をそろえること。
大見出し・小見出し・内容に分けて、それぞれ文頭をそろえると、情報が整理されて、どこに何が書かれているか、見ただけでわかりやすいノートになります。
2)ラインを引く。
ノート1ページ分の大きなフリースペースに書こうとするとバランスが取りにくいので、縦に1本ラインを引くといいですね。
ラインを引いて仕切ることで幅が狭くなって書きやすくなります。
例えば、左半分は黒板の内容、右半分は解説、というように、それぞれ書く場所に役割をつけてあげると整理しやすくなります。
ラインを引くのが嫌なら、折り目をつけるだけでもOK。
軽く折り目をつけておくだけなら越境しやすいので、あまりストレスにならずに書けると思います。
3)使う色はルールを決めて3色までにする。
4)あとから書き足せる余白を作っておく。
あまり完璧主義にならず、継続しやすいレベルで、ストレスがかからないルールを決めることが大切だと思います」
(太田さん)
★Real Voice「見やすいノートにするため気をつけていることは?」★
・「見やすいように細かい内容ごとに1行空ける。吹き出しを書いて、その中に自分で覚えやすいような一言メモを書く」(高2女子・福岡)
・「見やすいように間を空けるなどして、できるだけノートを広く使う。間違えたところには違う色で解説を書く」(高1女子・埼玉)
・「復習時にひと目で内容が分かるよう、一番上に大きく自分なりの題名をつける」(高1女子・東京)
・「ノートの左ページに予習をして、右ページに板書を書いている」(高2女子・大阪)
・「重要なところは大きく目立つように書く。隙間があると読む気がなくなるので、隙間を空けて書かない」(高1女子・東京)
・「あとから調べたいことや質問したいことは付箋に書いて貼っておく」(高2女子・愛知)
ちょっと気になる!ノートの書き方に関するギモン

※どんな工夫をすれば頭に入るノートになるか自分なりに考えてみる
カラーペンは何色使えばいいの?
・「色をたくさん使って色分けするほうがいいのか、最低限に留めるべきか」(高1男子・神奈川)
・「単語が覚えやすくなる色、集中しやすい色ってあるの?」(高2女子・北海道)
・「色ペンの上手な使い方を教えてもらいたい」(高2女子・福岡)
「ノートに使うペンの色の基本は3色。黒のシャープペン、一番重要な部分に使う赤ボールペン、一番ではないけれど大切な部分に使う青ボールペンの3色。色は赤と青でなくてもいいので、自分で色分けのルールを決めましょう。
重要ポイントを目立たせるために色分けをするので、色の種類が多ければ多いほど、どこが大事かわからなくなってしまいます。授業中にノートを取る場合、ペンを持ち替えることでタイムロスになり、書くスピードが遅くなってしまうというデメリットもあります。
授業ノートをそのまま暗記用にも使うなら、オレンジなど、赤シートで消えるような色を使ってもいいですね。東大合格生のノートを見せてもらったとき、一番大事なことを蛍光イエローペンで書いている人がいました。
蛍光イエローで書いた細い字は全然見えないけれど、見えないからこそ一所懸命に見ようとして覚えられるのだそうです。
青ペンで書くと集中力がアップするという説もありますが、色で覚えられるというよりは、文字の色を変えることで気持ちを切り替え、やる気スイッチを入れる、と考えたほうがいいでしょう。
自分の好きな色で構いませんが、基本3色で、自分なりのルールを決めて色分けすることが大事です」
(太田さん)
ラインマーカーって使うべき?
・「ラインマーカーを使うとノートに統一性がなくなってしまうので使ってないが、使ったほうがいい?」(高1男子・愛知)
「ラインマーカーを使うときも、ルールを決めて、色の種類を少なくすること。色を変えたり、ラインマーカーを使わなくても、鉛筆でアンダーラインをしたり、丸囲みをするだけでも、大切なポイントを目立たせることはできますよ。
どうしても覚えられないところ、絶対に忘れたくないところだけ、色ペンやラインマーカーを使う程度でも大丈夫だと思います」
(太田さん)
★Real Voice「カラーペンやラインマーカーを使うときに気をつけていることは?」★
・「赤シートで隠せるように、大事なところをオレンジで書いたり、緑のマーカーを引いたりする」(高3女子・北海道)
・「板書で白のチョークはシャープペン、赤は赤ペン、黄色は黄緑ペン、先生が大事だといったところは水色で書いている」(高1女子・愛知)
・「青のほうが脳に記憶されやすいと聞いたので、重要な箇所は青ペンで書いている」(高1男子・東京)
・「もう一度作り直さなくてもいいように、あらかじめ覚えたいところはオレンジやピンクのペンで書く」(高2女子・愛知)
・「重要なところにひくマーカーの色や、重要な単語を書くときのペンの色は、できるだけ対色を使うようにしている(同系色だと、せっかく色を変えているのにパッと見の違いをつけられないため)」(高3女子・兵庫)
・「色ペンは、ほぼ使わない。関係している情報には、矢印や吹き出しを使う」(高2女子・神奈川)
シャープペンとボールペンはどっちがいい?
・「シャープペンでノートを取るよりも、ボールペンのほうがいい?」(高1女子・静岡)
「シャープペンとボールペンは、どちらでもいいので、自分に合ったものを選びましょう。ノートの紙質と自分の筆圧に合ったペンが必ずあると思いますから、いろいろ試してみて、自分が一番使いやすいペンを探してください。
ノートを取ることは、継続して続けていくものなので、いかにストレスを感じず、書きやすいかがポイント。友達のお気に入りのボールペンを使ってみたけど、自分にはシャープペンのほうがいいと感じた、ということもあるでしょう。筆圧が強くて、シャープペンの芯がすぐ折れてしまうのがストレスになるなら、鉛筆を使うとか、最初に『この1本』と決めたとしても、どんどん変わっていっていいと思います」
(太田さん)
自分の目的に合ったノートの書き方をみつけよう!

※何の為にノートを取るか、どう使いたいかを1度考えてみては?
「ノートを取るときに一番大切なことは、目的を決めること。そのノートをどう使いたいかによって、書き方が変わってきます。
ノートは書いたら終わりではありません。
必ず見直しをして、知識の追加をして、ノートを育てていくことが大事。書いたノートを見直したり、テスト勉強に使ってみて、ここはもっと書いておけばよかった、この情報が足りなかった、と気づいたら改善していけばいいのです。自分の目的をかなえるため、勉強に役立たせるため、成績をアップさせるためにノートを書いているのだと意識しましょう。勉強方法と一緒で、これが正解というノートの取り方はありません。いろいろ試行錯誤しながら、自分が一番やりやすい書き方をみつけてください。
ノートは自分のために書くものです。授業を写すためではなく、自分が理解するために書くものだから、黒板をそのまま写さなくても、必要だと思ったことだけ書けばいいと思います。
きれいにノートを書いたことで満足してしまう人もいますが、ノートは映える必要はありません。きれいさよりも中身が勝負。このノートを書くことで定期テストでは何点取ろうか、このノートでどうやって勉強しようか、目的と使い方をイメージしながら、自分に合ったノートの取り方をみつけてください」
(太田さん)
文/やまだ みちこ 編集・構成/黒川 安弥
※この記事は2022年3月に取材された内容になります。
※スタディサプリ進路調べ 全国高校生200人を対象にアンケートを実施
関連記事
コーネル式ノートのとり方って?成績アップの秘訣はここにあった!
東大生の1日の平均勉強時間は7.5時間。勉強時間を増やすコツは?現役生50名に聞いた!
東大生のおすすめ勉強法!受験期にやってよかったこと・失敗したことを現役生50名に聞いた!
コクヨ「スタディプランナー」開発者に聞いた! 三日坊主にならないための目標・計画の立て方
関連記事リンク(外部サイト)
東大生の1日の平均勉強時間は7.5時間。勉強時間を増やすコツは?現役生50名に聞いた!
東大生のおすすめ勉強法!受験期にやってよかったこと・失敗したことを現役生50名に聞いた!
5分でテス勉革命!今回は【勉強アプリ】編
5分でテス勉革命!今回は【勉強アプリ】編
考え方・構成の仕組みがわかる! 志望理由書の書き方レッスン!(事例つき)
進学や高校生に関するニュースやトピックスを配信する記事サイトです。入試、勉強などについてのお役立ち情報や、進路に関する最新情報、また高校生ならではのトレンドを取材した記事をアップしています。
ウェブサイト: http://shingakunet.com/journal/
TwitterID: studysapuri_shi
- ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
- 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。