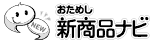青森の海を守ろう! 凛とした佇まいが美しい「津軽びいどろ」の『あおもりの海 盃セット』でハレの日を飾ろう

青森の伝統工芸品「津軽びいどろ」から、青森の海を守るプロジェクト「CHANGE FOR THE BLUE in 青森県」より誕生した『あおもりの海 盃セット』が登場だ。4つの海をイメージした、美しい盃は祝いの席を飾るのにぴったり! その4つの海を航海してみよう。
豊富な色ガラスから生み出される、美しい青森の工芸品

1977年に誕生した、北洋硝子(青森県)が製作する「津軽びいどろ」は、青森県伝統工芸品に指定された、日本を代表するガラス工芸ブランド。独自の技術・技法で作られるハンドメイドの商品を豊富にラインアップしている。

手づくりならではの柔らかく温もりある風合いと、豊富な色ガラスが特徴で、青系の色ガラスだけでもなんと10色! その青色を駆使して誕生した『あおもりの海 盃セット』(4個入り・販売価格 税込5,500円・発売中)は、青森の4つの海の色を表現した4種の盃のセット。シンプルで上品な箱入りだ。

青森の海を守る活動を推進するプロジェクト「CHANGE FOR THE BLUE in 青森県」に同社が賛同し、コラボ商品として誕生した作品だ。

東は太平洋、西は日本海、北は津軽海峡、中央は陸奥湾と4つの海で囲まれた青森県は、野生のイルカや海の絶景が多い。また、マグロ・ヒラメなど漁獲にも恵まれている。その海をゴミなどの汚染から守るべく、収益の一部は、寄付され活動に役立てられる。

左から盃 日本海/盃 津軽海峡/盃 太平洋/盃 陸奥湾
4種の盃に散りばめられている華やかな金箔は、晴れた日の海の煌めきを感じさせる。
「盃 津軽海峡」

日本海から太平洋へ潮が流れる津軽海峡は、世界でも有数な潮流の速い海。その影響もあり緑がかって見える海を、トルコブルーで表現した盃だ。

光に透かすと、凛とした穏やかさがある。ガラスのでこぼことした質感は、海のさざなみのよう! まるで、海に潜っているような感覚になるデザイン。

日本酒を注ぐと、表面の揺れがまるで海の流れのよう。

光に当たると、お酒が揺れて海の反射のようにキラキラしている。

グラスを持つたびに表面が揺れ、違う表情を見せる。

祝いの膳や、ちょっとした肴などにもぴったり。
「盃 太平洋」

雄大な太平洋に反射した空色をイメージしたスカイブルーを2色掛け合わせた盃。

日本酒を注ぐと、青色が一層鮮やかに見え、海の壮大さを感じさせる。

金箔が海を駆け巡る魚たちのようにも見える。
「盃 日本海」

自然が織り成す波と風を明るい青色のコバルトブルーで表現した盃。

深めの盃に日本酒を注いで底を覗けば、どこまでも続く深い海のよう。

散りばめられた金箔が、まるで藻のように上下に揺れて見える。
「盃 陸奥湾」

山や森に囲まれ、良質なプランクトンが流れ込む陸奥湾を深みのあるインディゴブルーで表現した盃。

日本酒を注げば、海の冷たさを感じるような、黒にも近い色合いで凛としている。

まるで金箔がプランクトンのようにキラキラと揺れて幻想的!

特別なグラスで飲むと、日本酒の味もまた一味違ったおいしさに感じるから不思議だ。器の美しさは、お酒の味をより味わい深く演出する。目で食べさせる、という日本料理にぴったり。
自分用に手元に置いても、大切な人への贈り物にもおすすめな盃で食卓を彩ってみては。
購入は公式オンラインショップ・楽天から。
関連記事リンク(外部サイト)
愛でるガラスの桜。青森県の伝統工芸品『津軽びいどろ さくらさくら』シリーズでお家でお花見を楽しもう!
夏を涼やかに彩る『津軽びいどろ MATSURI・HANABI』日本の美しい四季をガラスに込めて
【敬老の日】大切な家族に『プレミアムニッポンテイスト 竹虎』をプレゼントしてみてはいかが? その魅力を徹底レビュー!
色彩豊かで色々使える! 伝統工芸品「津軽びいどろ」から新シリーズ『色色豆皿』が新登場
映画コメンテーター・有村昆&世界的数学者・ピーター・フランクルらがコーディネート!千葉県下No.1家具ブランド『ROOM DECO』の体感型ショールームに潜入
お店に並ぶ新商品を実際に買って、使って、食べて、記事にしています。写真はプロカメラマンが撮影! 楽しいお買い物のナビゲーターとしてご活用ください!
ウェブサイト: http://www.shin-shouhin.com/
TwitterID: Shin_Shouhin_
- ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
- 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。