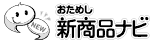記憶力ドリンク『キリン βラクトリン』は1日1本で思い出す力をサポート!

「え~と、あれなんだっけ…」年令を重ねると実感する記憶力の低下。キリンホールディングスはこの問題に立ち向かい、ついに記憶力の維持をサポートする機能性表示食品『キリン βラクトリン』を新発売した。乳由来の同社独自素材を使用した飲み物とのことだが、果たしてどんな味がするのだろうか。
手がかりをもとに思い出す力をサポート。3社合同の「βラクトリン(ベータラクトリン)」シリーズを発売

「βラクトリン」は、キリンホールディングスが協和キリン株式会社と小岩井乳業との連携の成果によって世界で初めて発見されたキリン独自の乳由来の機能性食品素材のこと。年齢と共に低下する手がかりをもとに思い出す記憶力※に対して、その認知機能の維持に役立つことが知られている成分だ。
※ホエイプロテイン由来のペプチドとしてヒトの記憶力(手がかりをもとに思い出す力)を維持することを世界で初めて発見 / Pubmed及び 医学中央雑誌Webに掲載された論文情報に基づく(2021年2月28日現在 ナレッジワイヤ調べ)

この成分はカマンベールチーズなどに含まれているのだが、その含有量はごくわずか。1日の目安量摂取しようとすると、40個(100g/個)を食べる必要がある。大金持ちの大食いファイターでなければ到底不可能だ。

そこでキリンはこれまで培った発酵技術をもとに、効率よく摂取できる素材を調査&研究。そうして発見された素材を使い、摂取しやすくした商品が『キリン βラクトリン』(100ml瓶・希望小売価格 税込216円・2021年5月11日発売)というわけだ。

内容量は100ml。ヨーグルトテイストのドリンクで、好きなタイミングで飲みやすくなっている。カマンベール40個がこの大きさになったと思うと技術の進歩は恐ろしい限り。1日1本、税込216円で記憶力が維持できるのならこんなにコスパの良いものはないだろう。

しかし、継続して飲み続けるには味も重要。早速確認してみよう。

1本あたりのエネルギーは34kcal、糖質は約6.9g
底に成分が沈殿しているのでしっかりと振ってから開封。見た目はカルピスのように白濁としている。

香りはヨーグルトだが、かなり薄め。

腰に手を当ててゴクゴクっと軽快に飲む。味はほんのりと酸味の利いたヨーグルト飲料と言う感じ。濃いめのカルピスのようで全く違うと断言できる絶妙な味。風味は少ないが、少しとろみがついておりしっかりと味を感じられる。甘さもほどよく、甘いのは苦手な人にもちょうどいい塩梅だ。

後味も特に気になるところはない。強いてあげるなら、若干独特な残り香があるかも? というくらい。とても飲みやすく抵抗感なく続けられそうだ。
協和発酵バイオ・小岩井乳業・雪印メグミルクからも「βラクトリン」シリーズ商品が新発売

「βラクトリン」を使用した商品は、キリンビバレッジのほか3社からも発売される。シリーズ商品は以下の通り。サプリメント、ドリンク、ヨーグルトとバリエーションがあるので、自分に合ったものを選ぶと良いだろう。
・協和発酵バイオ サプリメント「βラクトリン」4月20日発売
・小岩井乳業 乳飲料「小岩井 βラクトリンミルク」5月18日関東・東北にて発売
・雪印メグミルク ヨーグルト「記憶ケアヨーグルトβラクトリン」6月8日発売
今回紹介した『キリン βラクトリン』は、5月11日より全国のスーパーなどで発売する。
関連記事リンク(外部サイト)
本当に全く甘くないのか、『ウィルキンソン・ハード無糖グレープフルーツ』。散々騙されてきた甘くない缶チューハイ・アピール、今度こそ本物なのか!?
健康診断に引っかかっても大丈夫(!?)なゼロゼロ・ビール系はこれだ!『キリン のどごし ZERO』リニューアル登場
インフル予防で熱い注目を集めている紅茶。でもせっかく飲むならやっぱり美味しい『TEAs’ TEA NEW AUTHENTIC 日本の紅茶』!
5年ぶりの新商品! 丸搾り生茶抽出物で作られた『キリン 生茶 ほうじ煎茶』のお味は?【ほうじ茶】
【ペットボトル】猿田彦珈琲手がける新シリーズ『ジョージア ロースタリー ブラック』は雑味なしコーヒーの極みへ!【自販機】
お店に並ぶ新商品を実際に買って、使って、食べて、記事にしています。写真はプロカメラマンが撮影! 楽しいお買い物のナビゲーターとしてご活用ください!
ウェブサイト: http://www.shin-shouhin.com/
TwitterID: Shin_Shouhin_
- ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
- 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。