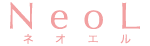DIY Issue : Interview with Takashi Asai from UPLINK / WebDICE

渋谷の映画館UPLINKはアート作品からメジャー系エンタメ作品まで、多様かつ良質な作品を上映し20年以上多くのファンに愛されるミニシアターである。また配給、ギャラリーやカフェレストランの運営、ウェブマガジン『webDICE』の発行、そしてクラウドファンディングサービス『PLAN GO』など、ミニシアターのジャンルに捉われない独自の方法でインディペンデントシーンの発信地であり続けている。この時代におけるインディペンデントビジネスのあり方を、UPLINK代表の浅井隆氏に訊いた。
UPLINK is a mini theatre in Shibuya which screens a variety of high-quality films, from delicate artsy films to the major entertainment works. It has been loved by its fans over the past two decades ever since it was founded. The service and facility also includes their own gallery, restaurant, and even their own web-magazine webDICE. Besides that, the cloud funding platform PLAN GO is a service UPLINK founded on their own which no other mini-theatre has yet developed. We had the honor to have a conversation with Takashi Asai from UPLINK and below are his thoughts on maintaining an independent business nowadays.
——浅井さんにとって”インディペンデント”の言葉が持つ意味とは?
浅井「日本語で”独立”を表す言葉ですよね。インディペンデントとは、自分で考えて行動し責任をとることだと思います。会社の場合だと、大手の資本の傘下にあるのではなく、例えばUPLINKの場合だと僕が株を100%所有しているので、社長である僕が、方針を決め、責任を伴う活動をすることだと思います」
——What does the word “independent” mean to you?
Asai: In Japanese, the word independent refers to the situation in which that one is able to support oneself. From my point of view, to be independent is to be able to think and act for oneself and take the responsibility. In case of a company, for example, rather than being under a major capital enterprise, I own 100% of the stock at UPLINK, and so I have to think about the policies and be responsible for all kinds of activities as its president.
——なるほど。映画のジャンルで言えば、近年特にメジャー映画とインディペンデント映画という枠組みは曖昧になってきているように思えます。
浅井「いつ頃からか、”インディーズ”という一つの音楽のジャンルがあるようになり、メジャー・レーベルの中にインディーズ部門が存在するといった、言葉の正しい意味ではなんだかよくわからない現象も起こって、”インディーズ”という名前が形骸化していますよね。また、映画で言うとハリウッドメジャー会社の一つFOXサーチライト製作の『シェイプ・オブ・ウォーター』はインディペンデント作品とは区分けはされませんが、ギレルモ・デル・トロ監督自身の精神がインディペンデントであるかどうかで言えばインディペンデントだろうし、彼自身がプロデューサーとして自分の企画を、スタジオを説得して通し、経済的リスクを一部負っているという点ではハリウッドのスタジオ映画ですけど、シンパシーを感じます」
——I see. Speaking of the movie industry, recently the line between major commercial works and independent films is getting kind of hard to define. What do you think?
Asai:The labels of indies films are emerging even in the major film companies just like a genre in the music industry since I don’t know when. The meaning of the name is merely accurate but somehow it is a phenomenon. Shape of Water, the film that came out recently produced by FOX, is not distinguished from independent films. However, the spirit of the director Guillermo del Toro indeed represents what independent means. He persuades the Hollywood studio into making the film as a producer and he himself was under the stress of the upcoming economic risks as well. That is very relatable.
——ジャンルとしての”インディペンデント”と、精神としての”インディペンデント”という区分けに乖離があるのですね。
浅井「定義付けが非常にややこしいことになっている。今は多くのトップ企業がインディペンデントスピリットを持つアーティストを起用することで『既存の概念をぶち破ろう』というイメージを広告によって打ち出そうとしています。ヒットしてお金持ちになったHIP HOPアーティストが、今はもう自分の居場所ではなくなったストリートの事情をリリックにすることと同じ違和感を、感じますね。結局、スタイルとしてのインディーズが存在していて、それがクールだと思われているという風潮があるということでしょうね」
——The difference between “independent” as a spirit and that as a genre is not easy to ignore, right?
Asai:I think it is really difficult to define that. Many top enterprise in the industry nowadays have this tendency to appoint artists who got the “independent” spirit just as a way to make good advertisement with the concept that already exist. It is just like those HIP HOP artists who make songs about the stories that no longer make sense because they don’t have the access to experience that anymore. It is sarcastically contradicting. After all, they are using the word “indies” as a label just because it is a cool thing to say to keep up with the trend.
——インディペンデントという言葉の難しさもありますよね。そもそもインディペンデントがクールと捉えられる風潮になったのは、何故なのでしょうか。
浅井「映画で言えば、デジタル化の影響が大きいと思います。35㎜フィルムのカメラは個人ではなかなか買えないし、扱う技術もない。しかしiPhoneやデジカメは手軽に手に入るし、今は色んなソフトもあるので編集も簡単にできる。それによって映画制作も興行も昔より格段に参入しやすくなりましたし、過去と比べても、遥かに多岐にわたった作品が世に出るようになりました。予算が限られたインディペンデント作品でもセンスの光るかっこよくて面白い作品が多く生まれ、新しいムーヴメントが起こり注目を集め評価されるようになったと思います。そのようなデジタル技術によっての革命は、他の分野のシーンにも起こっていますよね。ところで、NeoLの収入はどこから得ているんですか?」
——Sure. That is really a difficult issue. How did “indies” become a trend in the first place?
Asai:In the movie industry, I think the influence of this digital era we live in is enormous. You can not buy a 35mm film camera on your own and the technical problems are tricky. On the other hand, we have these digital devices that are very easy to get on with, like an iPhone. Also the softwares for editing are designed for all kinds of customers and that has made things much easier comparing to what it was like in the past. And that contribute to the variety of works coming out nowadays. You can make a independent film with interesting scenes even with a limited budget. The change and development in technology really is making an impact. I assume that it is happening in other fields as well. By the way, how does NeoL make profits?
——広告代理店が窓口となっての広告収入がメインです。
浅井「NeoLはカルチャーを軸としたインディペンデントなブランドイメージがあって、そこに広告代理店が目をつけて“この媒体を通せば若者にアクセスしやすい”と考えているんでしょう。編集部の企画がメインだとしても、広告記事が混入していることは、読者は広告というドラッグに侵されていくようなものだと思ってしまいますね。NeoLがドラッグディーラーのようですね(笑)」
——Mainly from the advertising revenue.
Asai:NeoL has this impression of an independent website centered on cultural issues. From the advertising agencies, this could be potentially considered as a way to approach young people. Even though the main duty is to focus on the editorial part, NeoL let those advertisement get into the article somehow like a virus, or some kind of drug. The readers are forced to take in both at the same time. NeoL is probably like a drug dealer in this digital era lol
——ディーラーの自覚もありますが、伝えたいことやピックアップしたいアーティストをお金がないからと切り捨てたり、制限したりということの方が媒体としてマイナスだと判断しています。
浅井「なるほど。カルチャー・ドラッグディーラーのそのやり方は伝統的なビジネスモデルとして紙媒体の時代からずっとあるものですから、ネットではキュレーションサイトなどがでてきてより巧妙になっていますよね。かと言ってスポンサーに頼らずサイトの閲覧を有料にするのも、拡散しづらいから違うと思うし。ネットでユーザーと直接繋がり、そのユーザーが欲するものを提供する、それがビジネスに繋がるということが出来れば理想なんですけれどね。世界観の良し悪しは別にして『ほぼ日』とかそうやって上場までしたからね。結局、自分たちのメディアや会社のブランド力をあげて、それをどうお金に変えていくかが重要だと思います。冒頭で言った『自分で考えて自分で責任を取る』というインディペンデントの精神があれば他から収入を得ることもあり、でもスピリッツは守るみたいな。実際問題、メディアの経済的独立性は難しいです。自分が運営しているメディア『webDICE』はUPLINKのお金だけでやっていますが、多くの改善点があるのにお金が回せていません。これは、常々頭を巡らせている問題でもあるので、今回自分だけのインタビューではなくて、NeoL編集部との対談という形式のほうが面白い記事になったかもしれないですね(笑)」
——That we are aware of. But we also are strict with picking the artists. It is crucial to separate those who are only limited by their financial issues from other medium.
Asai: I see. It is kind of like how they did it with paper media back in the days. And how internet media do curation work on the internet is getting more smart. However, I do not think it’s better way to make it to be pay site for not to rely on the sponsors’ support,because it is not something that can be spread. The ideal way is to be connected directly with the users and readers. To offer them what they want and profit from the deal.For example,a famouse culture web site”Hobo-nichi”is a success in business aside from whether it’s good or bad. Despite how it may seem when it comes to moral values, after all, it is important for independent media companies to consider how to make financial profits from the brand itself. Just like we have mentioned before, to be independent is to take one’s own responsibilities. Somehow we want to keep the independent spirit but we are also in need for financial support from others. It is really difficult for media companies to be independent financially. I am only using the money we gain from UPLINK to manage webDICE. But there are still plenty of problems need to be solved. It could be an issue for NeoL, too. This interview could be more interesting conversation between me and the editorial department of NeoL lol
——(笑)。でもその中で、あらゆる時代に沿って様々な変化をしっかり遂げ、インディペンデント精神を保っているUPLINKだからこそ、今回お話をうかがいたかったのです。
浅井「いろんな経験をして多少歳をとっている分、新しくDIYを始める人よりは世の中の仕組みはわかっているかな。僕自身その経験からなるべくカルチャー・ドラッグから離れようとはするけれど、経済的には苦労しますね。”お金”という会社にとっての血液をどうやって社会から得るかは常に付きまとう課題です」
——Indeed lol The story we want to focus on is how UPLINK manage to evolve and develop even though the time has changed. UPLINK has always kept the spirit.
Asai: I think it is just that I have experienced a lot and that granted me the point of view to see the structure of the world better than those DIY newbies. I say it is better to stay away from the “cultural drug”, but that is not easy to think about it from an economic perspective. It is always an issue when it comes to the challenge of putting money into the company from the society.

——課題に対してのUPLINKの攻めの姿勢の表れのひとつに、VOD(ビデオ・オンデマンド)など興行のやり方にも変化が起こる中で、12月にオープンするUPLINK吉祥寺があります。5スクリーン300席と、スクリーン数も座席数もUPLINK渋谷と比べ増加していますが(UP LINK渋谷3スクリーン144席)、これは今この時代にミニシアターをオープンするということを考慮してでしょうか?
浅井「UPLINKは今年で創立して31年目になります。設立当初から大きくなったけど、中小企業なので、守るのではなく、常に攻める必要があると考えています。よく、ミニシアターが減って大変ですねと、特にメディアの人に言われるのですが、みんなの認識が間違っている。僕らは渋谷で映画館を運営しているので、動員数が増えているという数字を持っています。日本は少子高齢化で人口は減っていますが、東京、神奈川は戦後ずっと右肩上がりで伸びています。実際、都内のシネコン、ミニシアターの動員は増えています。地方は正反対に厳しいですけど。なので、吉祥寺に映画館を作るというのは、ビジネスチャンスだと思っています」
——One of the signs that UPLINK has an aggressive attitude toward future development is that the change occurring right now like the way of VOD (Video on demand). A new mini theatre of UPLINK is opening at Kichijoji this coming December and it contains five screens with 300 seats. That is a lot more than what it has in Shibuya right now (3 creens and 144 seats). Do you consider it as a mini-theatre built for the specific time and place?
Asai: UPLINK has been founded for 31 years. Even though it has grown larger than before, as a small business, it is necessary to be aggressive to develop. All the people in the media industry think that mini-theatre is not an easy business to run because it is decreasing, however, that is wrong. The data shows an increasing tendency of people seeing movies at UPLINK in Shibuya. Even though the population in Japan is decreasing in general, it is not the same situation in Tokyo and Kanagawa ever since WWII. To tell you the truth, the cinema and mini-theatre in the city are working fine with a larger amount of customers. That is why I think opening a new one in in Kichijoji could be a good business strategy.
——なるほど。UPLINK吉祥寺ならではの上映作品の編成も考えていらっしゃるのでしょうか。
浅井「渋谷より2スクリーン多い分上映数も多くなるのでメジャー作品からインディーズ作品まで、より多岐にわたるジャンルの作品の取り扱いを考えています。渋谷では毎日10作以上を上映していますが、吉祥寺は5スクリーンあるので、メジャー作品からインディーズまで毎日20作品くらいを上映予定です。先日パリのポン・ピ・ドゥ・センターの近くのシネコンUGCに行ったら、そこは31スクリーンもあることに驚いたんですよ。その週にフランスで上映される全ての作品をメジャーやインディーズ問わず上映しているのを見て、どの映画を上映しようかと番組編成で悩むこともない、全部やればいいんだという映画館をいつか作りたいと思いました(笑)。一日中いても飽きないし、そういう場所を作って横に引っ越したらずっと映画観られるから最高だろうな」
——I see. Do you plan to screen something unique at Kichijoji?
Asai: Since it has two more screens at Kichijoji I think we will be screening more films, regardless of its genre. There are ten films being screened at UPLINK Shibuya everyday and so I am thinking that there should be about twenty being showed at Kichijoji. I recently went to the Cinema UGC near Paris’ Pont Piu do Center, I am really shocked that they have 31 screens there. It allows them to screen plenty of films, including major works and indie films. I want to have a theatre like that so that I don’t have to worry about what programs to organize and what to show. It would be the best if I could get all kinds of movies screening all day long. I think that I just won’t get tired of it lol
——ああ、それは最高ですね。
浅井「インターネットができてから音楽や映画を楽しむ環境の変容はあれど、リアルの空間、ようするにリアルな社会の中の映画館で楽しみたいと思う人は無くなっていません。UPLINKにとってもお客さんに映画を映画館に観に来ていただくことが最も重要なことです。リアルの空間に足を運んでもらうためには、UPLINKというブランドの信頼を得る必要があるし、そのためには、映画館もwebDICEも配給も自社ですべて管理し責任を負っているからこそ保つことの出来る品質が絶対的な鍵となってくると信じています。例えばwebDICEでは当初、グーグル・アドセンスをページにレイアウトして広告を掲示していました。でも広告が偉そうな顔してページに出てくるわりには、毎月の売り上げが数万円で少ないし、こちら側でコントロール出来ないような記事と関係のないバナーが出てくるのはうざくなり、やめました」
——That really is the best.
Asai: The internet really has changed the way people enjoy music and movies nowadays. The theatre and cinema is an actual place left for people to engage with the art works now. For UPLINK, it is crucial to give the customers the best experience to enjoy movies at a real dimension. That is way it is important for us to gain trust as a brand. We care much about the quality of not just the theatre, but also webDICE and the company. We want the quality to be good as promised.For example, when webDICE was first published, Google Adsense was laid out on the page and a bunch of fancy ads were popping out on the website all the time. The monthly sales are low, like only a few thousands yen. And it has nothing to do with the control of the banners. So I stopped that.
——ええ、何度も同じバナーが出て来たり、明らかに自分の嗜好を追跡されたバナーが出て来るのは個人的には気持ちいいものではないし、リアルの空間が面白いというのも同感です。
浅井「広告の露出量がその商品やサービスの購買数に繋がっているというのも結果としてあるのでしょうね。AIが同じバナーを出してくるというのは、”毎日会っている人に対して好感をもちやすい”という論理に近いと思います。広告主としてその商品を好きになってもらうために刷り込みを行うという論理のもとの戦略なのでしょう。でも、僕は天の邪鬼なところもあるので(笑)、毎日会わないような人のところに行きたいと思うときもあるし、定住せず旅をすることに憧れる。実際にそれを実行するとAIがアルゴリズムでオススメしてくるものよりも面白い出会いが多くなります。面白い出会いというのは、リアルな世界の方が多いんじゃないかな。ウチのスタッフには『今の世代にとってはネットの世界もリアルなんだからその考え方は古いです』といつも言われますけれど(笑)、僕はネットの中では情報が限定的になる罠が潜んでいると思うのです。自分の自由意志でネットサーフィンしているつもりでも、実際は与えられているものの中を見ているだけ。一方リアルの世界では街の中を歩いて電車に乗ってという中で、同じルートを何度も辿ったとしてもすれ違う人たちがその時々で違うわけなので偶然知ることのできる情報が得られるから飽きないですね。リアルな世界のアップリンクの映画館に来て欲しいという思いは強くあり、また今こそ観てほしいという映画もある。映画を作る上で製作者も時機に関しての思いはあるはずで、スピルバーグもトランプ政権下の今だからこそ『ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書』を『レディ・プレイヤー1』と同時進行で作ったわけです。そこで、映画館になかなか足を運べない人たちのために、新作映画を届けたいという思いもあり、オンラインで見る映画館、UPLINK Cloud(http://www.uplink.co.jp/cloud/)は有効な手段かなと思って立ち上げました。カルチャーを作り発信する立場として、様々なチャレンジを通してそれらをビジネスとして確立すること、それがインディペンデントであることを継続することに必要だと思います」
——Right. It is annoying to see the same banners all the time because it can track your personal preferences and make an ads based on that. Of course the real space and dimension is more interesting.
Asai: Apparently how they define one’s preferences is related to the products one buys on the internet. It is just like AI. A strategy based on a logical theory that people tends to like others who they get to see everyday. The program is designed to make people like the ads. However, I don’t find myself functioning like that. I sometimes want to go with someone I don’t get to see all the time, and I prefer traveling rather than settling. The encounters in the real world is far more interesting than the algorithms that AI made for you. The staff at UPLINK always say that the internet is also real to its users nowadays and so the way they think about it hasn’t changed much lol I just think that it is limited to get information only from the internet. Even though I plan to follow my own intentions while using the internet, I am being manipulated all the time. On the other hand, in the real world, even though you take the same train and follow the same routes everyday, the people you encounter changes and you get new information from the streets all the time. I have this strong desire for people to come to UPINK and see a film within this actual place. It is also important for the movie makers to think about the timing. Like, Steven Spielberg made the movie Pentagon the same time he directed Lady Player 1, under Trump’s regime. For those who can not make it to the theatre, I found this online theatre of UPLINK Cloud (http://www.uplink.co.jp/cloud/). I think it is significant to get through these challenges as a business while keeping the core of the independence to deliver all kinds of messages related to our culture.
photography Baihe Sun
text Shiki Sugawara / Ryoko Kuwahara
浅井隆
UPLINK代表/WebDICE編集長/未来の映画館プロデューサー
寺山修司の天井桟敷舞台監督を経て、1987年に有限会社アップリンクを設立。
映画配給、DVD、出版を行い、映画上映やイベントができる「UPLINK FACTORY」「UPLINK X」、ギャラリー「UPLINK Gallery」のほか、多国籍レストラン「TABELA」なども運営。ジャンルを問わない情報発信をするWebメディア「WebDICE」の編集長も務める。渋谷に映画館、イベントスペース、ギャラリー、マーケット、カフェがあるカルチャースポットを運営。オンライン・セレウトシネマ「UPLINK Cloud」を立ち上げ、さらに2018年12月には「UPLINK吉祥寺パルコ」もスタート。
http://www.uplink.co.jp/
都市で暮らす女性のためのカルチャーWebマガジン。最新ファッションや映画、音楽、 占いなど、創作を刺激する情報を発信。アーティスト連載も多数。
ウェブサイト: http://www.neol.jp/
- ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
- 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。