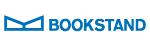月村了衛の軽妙でコミカルな連作短編集『おぼろ迷宮』

あらあ、月村了衛なのに甘口じゃないの、これ。
月村了衛は常に斬新な切り口で社会を描く犯罪小説の書き手であり、現代においても活劇魂を燃やし続ける作家である。鋼鉄のように硬く、燃え盛る炎のように熱い、というのが作家のイメージだろう。新作『おぼろ迷宮』(KADOKAWA)はどんな厳しい物語なのだろうか、と思いながら手に取ってみたら、だ。
四話から成る連作形式の小説で、第一話「最初の事件」は、大学生の三輪夏芽が夕暮れの雨に濡れながら走る場面から始まる。目指しているのはアルバイト先の「甘味処 甘吟堂」だ。だが駆け込んだ店で彼女を出迎えたのは、見知らぬ四十がらみの男だった。自分はアルバイトをしている者だと告げると男は、アルバイトなら他にいる、店主は自分で、代々ここで暖簾を守ってきたんだから、変なことを言わないで出ていってくれ、とえらい剣幕でまくしたてたのだった。しかも翌日甘吟堂に行ってみると、いつも通りの店主がいて、四十男の影もなかった。店主は、昨日も自分はいた、アルバイトを休むなら連絡をくれないと困る、と夏芽を詰るのである。
さっぱりわけがわからない。
狐に化かされたような心地で夏芽は下宿に帰ってくる。築五十年だか、六十年だかの「朧荘」、むしろおんぼろ荘とでも形容したほうがいいような老朽物件である。部屋に帰った夏芽は、スマートフォンで納得のいかない気持ちを友人にぶちまける。それはそうだろう。常識では考えられないようなことが起きたのだから。
そのやりとりを、おんぼろ荘の薄い壁を通して隣人に聞かれていた。
隣の部屋は、高齢老人の独り住まいである。表札から「鳴滝」という名字であることしかわからない。何をしている人物なのか、素性は一切不明だ。その怪しい人物が夏芽に、和菓子屋の謎について調べてみましょう、と申し出てきた。そして夏芽から話を聞くや、「なるほど分かりました」と言ったのである。なにがわかったのか。全部である。洋菓子店でオレンジケーキを食べてマンデリンを飲むだけのわずかな時間に。
こういう物語である。怪しい老人・鳴滝と三輪夏芽の人物配置は、バロネス・オルツィの『隅の老人』を思わせる。喫茶店とか甘味処が謎解きの主舞台になっているのも同じだ。だが鳴滝は紐いじりが趣味ということしかわからない隅の老人とは異なり、話が進むにつれてどういう過去を持っているかが明かされていく。最もページ数が多い第三話「最大の事件」は鳴滝の過去と無関係ではない内容なのだが、ここでは触れないことにしよう。
主たる登場人物は夏芽、鳴滝の二人と、老人を慕っているらしい剛田という大男である。どのくらいの大男かというと、エスプレッソカップの持ち手につっこんだ指が抜けなくなったくらいだ。夏芽の見立てでは、どう考えても堅気とは思えない風貌である。そんな男が付き従っているということで、鳴滝に対する疑念は募っていく。
第二話「次なる事件」はいわゆる特殊詐欺案件で、すでに死亡したはずの息子がある老婦人にたびたび電話をかけてきて金をせびっている。しかも電話だけではなく、実際に老婦人宅を訪れてもいるようだというのである。この不可解な一件にも、夏芽は鳴滝と共に首をつっこむ。うっかりして大学の前期試験を受けそこね、泣きついた指導教官から出された課題が、地域社会でインタビューを行い〈人の心に寄り添う〉とはどういうことかを知るためレポートを提出するというものだった。題材を探しているうちにこの一件を知り、義憤に駆られてしまったのだ。この事件で剛田が初登場する。夏芽の指導教官である榊静香准教授も、意外な形で後に物語に関わってくることになる。
一切の活劇要素を封じた作品である。いや、「最大の事件」で夏芽と鳴滝はあるものと闘うことになるのだが、あれを活劇と呼んでいいものか。北上次郎によれば、主人公が身体を用いて闘うことが活劇小説の基本ということになるので、それには合致していると言えなくもないのだが。まあ、読んで各自判断してみていただきたい。
主役二人以外のやりとりが軽妙に進んでいく。祖父と孫ほどに年齢が離れており、しかも鳴滝は持って回ったものの言い方をするので以心伝心とはいかず、しばしば行き違いや脱線が生じる。また、剛田と榊などの脇役が絡むことによって見えていた状況が変化することもあるのである。行動で物語が動いていく小説であり、筆致は実にコミカルだ。
シリアスなイメージが先行している月村だが、実は喜劇小説として読める作品も少なくない。たとえば、第172回直木賞候補になった『虚の伽藍』(新潮社)などもそういう小説で、常人とはまったく違った思考回路に陥ってしまった主人公が暴走する話である。あれは笑ってしまっていいのである。してはならない恋をした男女が主人公の『ビタートラップ』(実業之日本社文庫)もそうで、版元は悲劇的なスパイ・スリラーとして売りたかったようだが、二人の関係はちぐはぐなものでオフビートな犯罪小説の味がある。そうしたユーモアのセンスを前面に出して書いたのが、この『おぼろ迷宮』なのである。これまで月村作品を読んでこなかった人も、ぜひお試しいただきたい。
月村は、『悪の五輪』(講談社文庫)『欺す衆生』(新潮文庫)などの作品で戦後事件史を題材にした総合小説を試み、〈機龍警察〉(早川書房)シリーズで警察小説の外構を用いて国際情勢を描くというように、困難な課題に果敢に挑戦する作家である。根底には他の誰も書かないようなおもしろい小説を求める気持ちがあるはずで、決してシリアス一辺倒であるわけがないのである。たくさんある引き出しを少しずつ開けて、読者に見せてくれている。
読めばわかるのだが『おぼろ迷宮』は真っ当な正義が描かれた小説でもあり、これまでの月村作品と通底する部分もある。ここから他の作品に手を伸ばすことももちろん可能なのだ。多彩にして多才、月村了衛という作家を一人知っていると、当面は読むものに困らないはずだ。一家に一冊、いや一家にひとり月村了衛を。
(杉江松恋)
- ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
- 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。