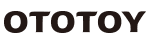【カナダインディー便り】夢のような現実。東京国際映画祭レポートby Alex Henry Foster

カナダのインディーレーベル〈Hopeful Tragedy Records〉で働くモントリオール在住の日本人・Momokaが、現地にいるからこそ分かるカナダの音楽シーンを紹介する【カナダインディー便り】。
今回は番外編として、2024年10月28日(月)〜11月6日(水)の10日間、東京にて行われた『第37回東京国際映画祭』の様子を、現地に訪れた〈Hopeful Tragedy Records〉所属アーティスト・
初めての『東京国際映画祭』へ
毎年、日本を訪れるようになってから、早10年ほどが経つだろうか。これまで一度もデジャヴのような感覚になったことや、見飽きたなんてことを感じたことはない。ただ街中を歩くだけでも、僕にとっては冒険だ。至る所に発見があり、「なんの変哲もないように見えること」に対して心を開ける人にとって、たくさんの驚きが待っている。まるで目に見えないスピリチュアルな流れのように。考えを巡らせるものがそこら中にある。
あらゆるところに考察の余地がある一方で、ほとんどの人にとって、それはどこにでも存在するものだったりする。だからこそ、最も重要な要素はカメラで捉えることができないんだ。美しさは、それが持つ謎のように、経験され、消化されなければいけない。でも、そうするためには、自分が自分であるために不可欠だと思っているものを手放す必要がある。それは文化だったり、社会的ステータスだったり、信仰や教育だったり。どこへ行くにもつねに連れていっているもの。この特定の“航海”は、僕らが持っていくものを特に必要としていない。というのも、僕らを内側から変えるものは、「目を喜ばすもの」とは限らないからだ。美しさは別の側面、別の意味、別の含みすら持つ。そういう心構えで、僕は今回初めてとなる『東京国際映画祭』へと参加した。

日本文化が僕の想像を掻き立てるものであるように、映画というのはいつだって、夢を見るために、そして目で見えるものや制限されるもの、または絶対的だと思うものを超えて、「現実を探るための恵み」を生んで育てる、すばらしい方法だった。映画によって、自分の世界を広げられるんだ。だから、僕にとっては、煌びやかなレッドカーペットやイベントのグラマラスでハイプロファイルな要素のためにこの祭典に参加したのではなく、映画が僕に与える解放的な魔法のために参加した。
全く見知らぬ人、お互いに全くかけ離れている人たちが、物語を、映像を、キャラクターを、色彩を思い描き、そこに命を与えてくれる。だからこそ、他の人たちの人生に信じられないほどの影響を与えることができるんだ。それに僕は感動するし、それは僕らに深く消えない印を残してくれる。僕はそのおかげで、色々と物思いにふけり、考え、思い出し、他の人と分かち合うことができる。だからこそ、僕はここにいるんだ——ありえない魔法のためにね。そして、世界的に皮肉が満ち、個人的な幻滅の時代において、魔法は取るに足らない事柄ではない。子どものころのように心を動かされるような特別な場所があるとすれば、それはここだと思った。
活気、ざわめき、回想。再認識した“魔法の力”
映画祭の熱気は目でも耳でも感じられた。でも、僕がここに来たのは、ショートクリップや数行のレビューを書くためじゃない。この場の雰囲気や魂を感じ、活気溢れる場所や空気感を体験しに来たんだ。そして、そのざわついた忙しい空間も確実にその体験の一部だった。目の前で繰り返される燃え盛るループのなかに、自分自身や自分の生きかたが投影されているのを感じた。
そして僕は、他の人たちのように慌ただしい義務を負わずに済んだことに、どこか感謝していた。たとえ、すべてがすばらしかったとしても、それぞれのニュースメディアに情報を提供するためにキーボードを叩く音の大きさには、心奪われるものがあったよ。僕はエンターテイメント・マシーンの裏側にいたんだ。その光景は、人が簡単に使い捨てのオブジェにしてしまいがちな「芸術作品」の創作過程とはかけ離れた印象的なものだった。少し前までは遠い夢でしかなかったものを実現するために最大限の献身が必要なことを除けば、現在ではすべてが一瞬で決まってしまう。自分の疑い、恐れや不安を、人生を変えるかもしれないプロジェクトへと投資するには、一生分の勇気が必要だ……でも、なんのために? 誰のために? そうするのは美しい狂気だよ。特に、これまで注ぎ込んできたものが最終的にはネオンライトで満たされた混雑した部屋に行き着くと知っているからこそ。ちょうど僕が立っていたような場所だよ。そこでは、すべてのプロジェクトが締め切りや他の外的な要因の混乱に対応しなければならない人たちの手に委ねられる運命なんだ。誰もが超高速で進むコミュニケーションゲームのなかで役割を果たしている。注目を長く浴びる人もいれば、そのすべてを失う人もいる。不公平さなんて関係ないんだ。すべてのクリエイターはそのルールをわかっているけれど、それがエンターテインメントだと感じる人なんてほとんどいない。それでいて、魔法があるなんてね。

だからこそ、僕と同じように野外上映を楽しむ夢想家たちに囲まれて、束の間のひとときを過ごすことができたのは、とても新鮮だった。さらに特別なことに、僕が最初に観た上映作品は、アニメ『UFOロボ グレンダイザー』だったんだ。フレンチ・カナディアンの間では『Goldarak』として知られている作品で、子どものころ、毎週土曜日の朝にTVの前に座って観ていた思い出がある。この屋外上映が、昔、両親がかろうじて家賃を払えたような質素なアパートへと僕を引き戻した。貧困は、年齢や民族に関係なく、悲惨な状態だ。そこから抜け出そうとするのは、さらにフラストレーションが溜まる。でも、地球の反対側で作られたアニメを観るのは、母がいつもいっていたことと通じる。「夢を見ること、そこには自分の世界を変える力がある」ってね。何度も繰り返しいっていたんだ。自分の潜在能力を引き出し、制限を超えて、望むところに自分を投影することができるのだと。
そして、いま、僕は日本にいる。お気に入りのアニメのほとんどを産んだ場所に。アニメを観ていたころはそれが日本のものだなんて知らなかった。でも、いつか世界を旅できるならどこへ行きたいかと尋ねられたとき、デューク・フリード(フランス語版ではアクタリュス)のように宇宙を旅したいと答えていた記憶がある。母は笑って「宇宙旅行へ行ったらお土産持って帰ってきてね」と、教室で先生が僕らに教えていたのとは全く違う視点で答えてくれたよ。学校の先生たちは「君たちのようなキッズが、夢を見るなんて大それたことだ。生き残るために、役立つ職業を見つける必要がある」という感じだったから。世界から新たな探検家が生まれる可能性を奪う、酷い方法だよね……。僕は、次の映画上映に向かう前に、社会不適合者たちのチームを集めて、星空をもっと速く駆け抜けようと呼びかけるデューク・フリードを観ながら、信じられないほどありがたい気持ちになった。
「感じるのを避けている気持ち」を芽生えさせてくれた『敵』
もしも、あえて厄介なことをあげるとしたら、僕のようにオールアクセスのパスを持っている場合、”探検”する意味を忘れがちになってしまうこと。だから、観てみたい映画を選ぶだけでなく、普段「感じるのを避けている気持ち」を芽生えさせるようなものを選びたいと思った。そのためには、あらすじを読み、監督についてリサーチし、同じ脚本家の過去のプロジェクトについて調べるなどの時間が必要だった。その作業は、結構好きだよ。夜中にいろいろと考えながら選んだものが、朝になると変わったりもした。ジレンマ、ためらい、直感的なチョイス。それらを含めて、この儀式は満足のいくものになる。気になったり興味が湧いたりしたいろいろな映画を観ることができた僕だけれど、今回東京グランプリ/東京都知事賞を受賞した、吉田大八監督・脚本の『敵』が特に印象に残ったよ。淡々と描かれているのが好きで、反射的な動きが良かった。独特なリズムは、批評のためではなく、物語を支えるため。視聴者をこのユニークな感情の流れへと導き、その催眠術のようなリズムは暗い部屋にいる一人ひとりを、完全に物語と一体化させた。そこには、空間も時間もなかった。日本への旅がそうであってほしいと願っていたことを、その正直な事柄を通して包み込んでくれた。
『敵』は明らかに、あの暗い部屋にいたオーディエンスそれぞれにすばらしい印象を与えたことだろう。映画が終わったあとも、みんな余韻を楽しんでいたから。次の映画や記者会見のスケジュールがあったかもしれない人たちのことを考えると、それだけでも、すでにすばらしい達成だ。会場全体が感傷的な雰囲気に包まれたあと、またさまざまな言語が飛び交う熱気に溢れたノイズが、戻ってきた。予期していなかった展開や、いままさに感じている気持ちを分かち合いたいと思うような。映画についての会話は、宿泊先に戻る僕らの間で、一杯飲みながら続いたよ。真の芸術は、人を集めるものであり、交流を生むことを示すものであり、驚くべきほどの明瞭さを与え、僕ら自身と僕らが引き寄せられる世界への見方が変わることを示すような純粋さを持っている。

映画が普遍的な人間のテーマ、たとえば、ときの流れ、シンプルさに祝福された平和、内なる静けさの荘厳さ、そして、僕たちの存在意義が薄れていくなかで生活を彩るために必要な幻想との対比、身体と心がゆっくりと衰えていくこと、やがて訪れる死への予感、これらすべてを結びつける孤独感を、これほどまでに繊細かつ優雅に描くとき、それが僕たちの心に深い反応を引き起こさずに通り過ぎることはないだろう。
そして、それは大いにそうなったんだ。僕らは原作者である筒井康隆さんについても話したよ。自分の作品が3次元の映像作品となるのを観るのは、すばらしい気持ちだろうってね。僕たちが取り上げたテーマの持つ親密で厳粛な性質が、冷静で真面目なアプローチを求めたのはたしかだったけど、それは映画と同様、本来想起されるべき重々しさとは程遠いものだった。それは静寂で、落ち着いていて、ほぼ無垢で、とても面白いものだった。ニューヨークのオープンスペースのような日比谷ホールのエリアに、みんなで集まって、その夢のようなロケーションで、パリ(フランス)、ロンドン(イギリス)、アンカラ(トルコ)、ラバト(モロッコ)などから来ていた夢想家やレポーターたちと、とてもシリアスなディスカッションを楽しんだ。大事なことが「一見したときに見えるか見えないか」ではないのであれば、なにも間違ってはいないというもうひとつの証拠だ。
僕らの率直な意見交換が、すぐに陽気なものとなり、そしてゆくゆくは音楽の話題、映画のなかで音楽がどれだけ大きな役割を担っているかについて話した。映画『敵』においては特に、音楽が重要な要素であるということもね。コンポーザー・千葉広樹さんによって、まるで見えない糸のように完璧に図られた音楽は、僕らを物語へと引き込む。彼はすばらしい感情の伝道師であり、音のメインキャラクターとして、概念的なアプローチと哲学的なプロセスの破片を想起させる。それは、才能豊かな日本のコンポーザー堤裕介さんが、フェスティバルのオープニングの翌日にコーヒーを飲みながら話してくれたことだ。この時間は、僕自身の直感的な芸術性を大いに啓発してくれたし、僕が観た毎回の上映において、心を解放した発見の道へと導いてくれたすばらしい出会いだった。
豊かで驚きに満ちたフェスティバルの数日間は、日本の典型的だけど華やかなセレモニーで締めくくられた。個人的にはクリエイティブな芸術作品に賞を与えるというコンセプトがあまり好きではないものの、吉田監督の献身的な作品が認められたのは素直に嬉しかった。きっと東京国際映画祭という枠を超えて、この映画はより長く息をし続けられるだろうから。世界的に、コンピューター化されたスーパーヒーローやさまざまな映画のリメイクが増えるなかで、いまでもこういう作品が人の心に訴えかけ、個々人を繋げ、自分の考えや夢を形にするために「刺激を与える魔法の力」があると信じている人たちに届くのを見るのは、とても新鮮だった。日本は再び僕のイマジネーションを驚きの渦に巻き込み、次の目的地である『マラケシュ国際映画祭』への道を開いてくれたよ。夢のような可能性と希望、そして約束に満ちた、もうひとつの魅力的な目的地へと。
コラム、写真:Alex Henry Foster
翻訳:Momoka Tobari
アーティスト情報
Alex Henry Foster
・公式サイト : https://alexhenryfoster.com/ja/
・X : https://twitter.com/alexhfoster
Momoka
・X : https://twitter.com/momoka_tobari
・〈Hopeful Tragedy Records〉 : https://htrstorejapan.com/
★連載【カナダインディー便り】アーカイブ
https://onl.sc/aBXbF9p

- ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
- 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。