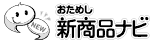【睡眠の質向上】『CHILL OUT(チルアウト) スリープショット』まったりできる寝る前ドリンク!【機能性表示食品】

朝、起きたときに疲労感が残っている。睡眠の質を高め、効率的に仕事をこなしたいという人に向けたリラクゼーションドリンク『CHILL OUT スリープショット』が登場した。いま話題の「CHILL OUT」を商品名に冠したドリンク。実際に飲んで、リラクゼーション効果を検証してみた。
飲めば”まったり”、昨今注目の「睡眠の質向上」を実現するテアニン・ギャバ入りカフェインフリードリンク!

Endian『CHILL OUT スリープショット』は就寝前に飲むと翌朝の目覚めが違う!
桜の季節もあっという間にすぎ、新生活に慣れてきた時期。気を張っていた反動で、ドッと疲れが出ているという人もいるだろう。朝起きたときに疲労が抜けない。それは睡眠の質が良くない可能性もある。そんな人におすすめなのがEndian(大阪府)から発売された機能性表示食品『CHILL OUT スリープショット』(100ml瓶・希望小売価格 税込270円・2022年4月18日発売)だ。

このイメージキャラに見覚えがある人も多いはず
そもそも「CHILL(チル)」とは何だろうという人もいるかもしれない。「CHILL OUT」とは「冷静になる」「落ち着く」といった意味で、これが転じて若い層には「まったりする」「くつろぐ」といったニュアンスで話題になっている言葉だ。
なお、最近テレビCMで目にした人も多いリラクゼーションドリンク「CHILL OUT」は、同社の商品で同じく4月18日にリニューアルされている。

「CHILL OUT スリープショット」には起床時の疲労感や眠気を軽減するL-テアニンが配合されている
「CHILL OUT スリープショット」は、従来品の2倍以上の「L-テアニン」が配合されている。これは高級なお茶や新茶に多く含まれる成分で、睡眠の質を向上させ、起床時の疲労感や眠気を軽減する機能があるという。

健康的な生活をサポートする「ギャバ」が多く含まれ、しかもカフェインフリー
『CHILL OUT スリープショット』には、L-テアニンのほか、野菜や果実に多く含まれるアミノ酸の一種「GABA(ギャバ)」が従来品の10倍以上も含まれている。これにより、快適な生活をサポートしてくれるはず。また、保存料や着色料が不使用で、就寝前でも安心なカフェインフリー。しかもリラクゼーションをサポートするオリジナルフレーバーを、なんとAI技術で開発したという。
それでは、実際に『CHILL OUT スリープショット』を飲んで、CHILL OUTできるかどうか検証してみる。
『CHILL OUT スリープショット』リラクゼーション効果を感じるシトラス&ハーブ風味にホッとした!

グラスに注いでみると、ほぼ無色透明
「CHILL OUT スリープショット」は、ほぼ無色透明。匂いも特徴的なものは感じない。ひと口含んでみると、やや酸味があるフルーツ系の風味。それでいて、後味はスッと清涼感があり、クールダウンできるように感じる。シトラスとハーブが配合されているから、落ち着きのある風味が形成されているのだろう。

飲んでみると香りが鼻に抜けて心地よい。まさにリラクゼーション効果
記者はPCによる作業の後に、就寝前に「CHILL OUT スリープショット」を飲んでみた。いわゆる頭脳労働を根詰めて行うと、疲労感があるのだが脳が昂ぶっていて、なかなか寝付けないということがよくある。そんなときに、この「CHILL OUT スリープショット」を飲むと、頭と身体をクールダウンしてくれる感覚になる。そして、ベッドに横になった途端に寝落ちしてしまった。
寝る前に摂取すれば睡眠の質が改善する!

寝る前に1本を習慣にすれば、翌日スッキリと仕事に向かうことができる!
「CHILL OUT スリープショット」は、同社の実験によるとノンレム効果に含まれる深い眠りの時間の割合が増加する傾向が見られるという。さらに、深い睡眠状態に関連する脳波成分「デルタ波」の強度が増強し、中途覚醒1回あたりの時間が減少したという。
このことが何を意味するかというと、単純に「CHILL OUT スリープショット」を摂取すれば睡眠の質が改善するということだ。
「CHILL OUT スリープショット」は、全国のドラッグストア、スーパーマーケットで購入できる(一部店舗を除く)。
関連記事リンク(外部サイト)
【免疫アップ】国民的乳酸菌・シロタ株を史上最高菌数で! 『ヤクルト1000(Yakult1000)』【乳酸菌】
【デカフェ】やさしいミルクの味わいに麦芽がマッチ! カフェインゼロの『TEAs’ TEA NEW AUTHENTIC 麦芽オレ』
【熱中症対策】いざという時の『経口補水液』飲み比べ OS-1/アクアソリタ/経口補水液 アクアサポート〜どれがおいしい?【脱水症状】
ミルクとココアで栄養素もバッチリ摂れる『GREEN DA・KA・RA ミルコア』
【免疫サポート】プラズマ乳酸菌と青汁のパワーを同時にゴクリ『プラズマ乳酸菌免疫ケア青汁』
お店に並ぶ新商品を実際に買って、使って、食べて、記事にしています。写真はプロカメラマンが撮影! 楽しいお買い物のナビゲーターとしてご活用ください!
ウェブサイト: http://www.shin-shouhin.com/
TwitterID: Shin_Shouhin_
- ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
- 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。