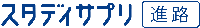【藤原和博×西野亮廣の未来講座④】情報編集力で思考するとは
1時間目「情報編集力で思考する」 藤原和博
藤原:
今日もちょっと前半は僕が君たちの脳をかきほぐすというか、前に言ったように情報処理力で、パターン認識脳だといいアイデアが出てこないので、これを情報編集力側に持っていきます。
“ジグソーパズル型学力からレゴ型学力へ”という言い方もするんだけど、この情報編集力側に頭を持っていくと、すごく頭が柔らかくなって、いろんな企画が出やすい、そして企画が通りやすくなる。

その練習をしてもらいたい。葬式の話から練習しましょうか。
葬式には多分、学生服を着ていったり、喪服に近いもの、黒に近いものを着させられたと思うんだよね、小さい頃。
大人もみんな喪服を着ていたと思います。
“喪服は黒”というのが常識なんだけど、なんでなのか。
喪服はなんで黒いのか?
もし、たとえば小学校3年生ぐらいの子が、君たちに問いかけてきたら、なんと答えるか。
そこで答えられないとかっこ悪いじゃん?
じゃあなんで喪服は黒いのか、ブレストしてみましょう。
【ブレスト後】
藤原:
喪服のルーツを考えてもらいたいと思います。
実は、日本の喪服というのは明治に入るまでは黒じゃなかった。
白だったの。
君たちも潜在的に知っていると思う。
時代劇で見る切腹のシーンで、黒いのを着ている人いないでしょ。
みんな白だよね、喪服も含めて正装は白だったんですね。
ところが諸外国から来る、たとえば大使や国王の代理だったり、ヨーロッパとかアメリカではどうかな?みんな燕尾服みたいなのを着て来るでしょ?
それを見た明治の元勲たちがヤバいぜ!となった。
国際的には黒が礼儀らしい。
当時の日本は、イギリス、フランス、ドイツから、法律から憲法から軍の制度から交通、警察の制度なんかに至るまで全部輸入してきた、そういう時代です。
だから、とにかく黒じゃないとヤバいらしいとなって上層部から変わっていったんです。

ところが日本の民衆は偉くて、そんな動じなかった。
だから白もまだ全然残っていた。
それがガラッと変わっていくのは昭和です。
昭和は戦争の歴史でした。
戦争も末期になると、毎日毎日お葬式じゃないですか。
その頃、自分で喪服を持っている人はなかなかいなかったから、レンタルするわけです。
レンタルで黒い喪服と白い喪服、両方とも貸してたんだけど、結果的に毎日お葬式に出るような状況になると、どっちが汚れないかってことを民衆が選んで、自然に黒になっていった。
そんな大したことない理由で、そのようなことが起こっているわけです。
ところがその前の歴史を調べると黒が流行っていた時期があって、平安時代に貴族がこのフォーマットを決めるんだけど、最初に決められた喪服の色は白だった。
1300年ぐらいの時を経て白が途中で黒になって、江戸期までに白に戻り、それが明治期を経て、昭和平成で黒くなっている。

白から黒、黒から白。
今、たまたま黒になってるだけってこと。
だからこれが50年後も黒が常識かどうかっていうのはまったく分からないですよ。
意外と常識とか前例っていう風に僕らが捉えているもので、無条件に反応するような感じで着たりとか買ったりしている物って、割と疑わしいってことです。
というわけで、処理力から編集力に頭を切り替えるときに最も大事なことが二つあって、一つは遊び心。
どちらかというともう一つの、複眼思考が大事です。
“一つの物事を片方からだけから見ない”右だけでなく左、上からだけでなく下から、前からだけでなく後ろから見るとどうか。
常識や前例を上手に疑うと、前回から言っているクレジット、信用力がアップしますので、これから信用力を上げたいのであれば、ただ単に常識、前例を信じないで一旦疑ってみる。
自分の頭で考えることが大事です。
情報編集力(複眼思考)で自分プレゼンを考える
藤原:
最初なんですが、4つの方法で自分のプレゼンをしてもらいたいんです。 1.キャッチフレーズ(つかみ)型
2.+(プラス)モードの
3.-(マイナス)モードの
4.Q&A型
初対面の人に会ったとき、ふっと何を言うか。
ということでキャッチフレーズ、つかみ型の自分プレゼンですね、まずはこれをやってみてほしいんです。

できたら相手にちょっと笑ってもらえるような、そういうつかみが取れるといい。
相手が分かっていることをそっと言うと笑っちゃうとか。
ということは、プレゼンは頭を常識モードから切り替えて、情報編集力側に切り替えて、自分のキャラを編集する必要があります。
ところが日本のビジネスパーソンは、プレゼン、プレゼンと言っているけど、全然プレゼンになってないものがいっぱいあります。
それは何かというと、“エクスプラネーション”といって自分の頭にあること、たとえばAとかBがあるとする。
Aということを“解説”する。
自分の頭の中にあることを、もう必死になって解説する。
プレゼンと言ったら相手の頭の中が大切。
相手の頭の中に映写室があると思って。

映写室にどんな映像を映すかということだけを意識しないと、プレゼンにはならない。
相手の頭の中にC、D、Eの世界観やイメージしかなければ、Aと言ったところで理解不能なんですよ。
相手の頭の中にあるC、D、Eを使って編集してあげなきゃいけない。
頭の中にあることを組み合わせて編集してあげると、プレゼンが通りやすい。
なぜか。
それは自分の考えだと思うからなんです。
他人の考えなんだけど、自分の知識、世界が再編成されるから、自分が考えたことと勘違いするわけです。
だからこういうプレゼンはすごく通りやすい。
次の「+(プラス)モードの」は簡単。
自分が得意なこと、任せといて!みたいなこと、知識があるとか、集めているものとか、自分の+モードで自分を語ること。
通常、君たちは自己紹介やってと言われたら、これをやっていると思う。
これは別に相手のことをあんまり考えなくてもいいです。
自分の得意なことをまず伝えてください。
【自分プレゼン実施】
藤原:
+(プラス)モードはね、あまり疑問はないと思うんです。
でも+(プラス)モードがあれば-(マイナス)モードがあるわけです。
-(マイナス)モードっていうのは、まあそうですね、挫折や失敗や病気で自分を語ることですね、こちらもやってみましょう。
-(マイナス)モードが絆を生む
藤原:
僕が10年間で1200回ぐらい講演をしました。
そのうち500回600回はこの練習をやっているんだけど、100人200人の会場でやると7割方が-(マイナス)モードの方に手をあげます。
それは人間のコミュニケーションの特徴で、基本的にマイナスの話、挫折、失敗、病気の話の方が成功談だったり相手の自慢話よりもインパクトがあるからなんです。
-(マイナス)モード、つまり失敗とか挫折とか病気で共通点があると、その方が絆が深まる。
絆が深まる、という言い方をします。
だから-(マイナス)モードって大事なんです。
君たちはこれからの人生、そうだな17歳から今の倍の年になるまでは恥をかき通しでいいの。
恥はいっぱいかいた方がいい。
そこでどれくらい失敗や挫折の話題を貯め込めるかというのが、そこからさらに先の
40代、50代、60代、70代、80代、90代までの話のネタになる。
さらに話をおもしろおかしく語れた場合には、多くの味方をつける資産になる。
自慢話を1時間もされたらさ、どんな親友だってひいちゃうじゃない?(笑)。
それよりも初めての人でも次の瞬間に、ちょっと-(マイナス)モードの話を真摯にされると、こちらのエネルギーが入るという感じがするんですよ。
人間と人間の関係っていうのは+(プラス)モードだけでは語れない。
+(プラス)と-(マイナス)モードの両方、とりわけ-(マイナス)モードが出てきたときに強くなる可能性があるんです。
今度はQ&A型です。
隣同士の2人、もうだいぶ解り合ってますよね。
だけどここでさらに、片方が物凄い勢いで個人的な質問を浴びせてほしいんですよ。
血液型は何?からでもいいですよ。
個人的な質問をとにかく2分間浴びせまくり、答えを聞いてもらいたいんですけど、何をやってもらうかというと、2人の間の共通点を探ってほしい。
少しレイヤーが下の、2段階くらい下のものが引き出されたとき、「えー、そうなんだ!」という感じで、感動までいかなくてもいいけど、ちょっと嬉しくなっちゃうようなこと。
双方がちょっと嬉しくなっちゃうということはレアなケースだと思います。
それをどれくらい早くに探り出せるか。
何を言いたいかというと、インタビューする側のインタビュー能力ってだけじゃないということ。
初回にも強調したと思うんだけど、脳と脳をどれだけ早くつなげることができるかということ。
“脳と脳をどれくらい早くつなげることができるコミュニケーション能力があるか”ということです。
これはすごく大事な情報編集力側の力なので是非試してください。
ではやりますよ、ちょっと嬉しくなっちゃうような共通点探しです。
【Q&A型共通点探しゲーム実施】
藤原:
これやるだけで絆が見つかりますよね。
最初の+モードで好きなこととか興味みたいなことを聞いていった人は多いんじゃないかと思うんですよ。
たとえば今度は-モードだけで共通点を探って、見つかるとかなり絆が深くなる印象があると思います。
共通した病気になったことがあるとか、深い挫折の経験が、割と共通したものだったみたいなことはすごく絆になりやすい。
コミュニケーションの本質は“共有する”こと
最後にちょっと教養あふれることを言っときます。
これ覚えておくと頭よく見えるんで(笑)。
コミュニケーションって言うじゃない?コミュニケーションでよく使うと思うんだけど、このコミュニケーションの語源が「communis」というラテン語です。
「com」という接頭語がついている言葉は大体でこのラテン語の「communis」が由来です。
コミュニケーションもそう。
どんな英語がありますか、「com」がついてるもの。
communityは共同体という意味ですね。
commonは公的なとか、共通なとか。

communicationとかcommunismとかcommon、
これらの意味から考えると、どうやら伝達するっていう雰囲気じゃないよね?
「communis」というのは、「共有する」という意味です。
自分の頭にあることを伝達するのはコミュニケーションではなく“2人の間の共通点を共有する、というのがコミュニケーションの本当の意味”
だということを覚えておいてもらいたい。
君たちが今やった共通点を探るっていうことが大事になんだって、覚えておいてください。
その技術がある人は、この情報編集力が高いってことになります。
このクラスでずっとテーマにしている「信用」という力が上がっていく。
相手との間に共通点を探れる人の信用が上がっていくということなんです。
投稿【藤原和博×西野亮廣の未来講座④】情報編集力で思考するとはは【スタディサプリ進路】高校生に関するニュースを配信の最初に登場しました。
関連記事リンク(外部サイト)
小論文完全マニュアル② 小論文は序論が命!点が取れる小論文の書き方ガイド
【藤原和博×西野亮廣の未来講座③】「信用」とは何か
【藤原和博×西野亮廣の未来講座②】「お金」とは何か
進学や高校生に関するニュースやトピックスを配信する記事サイトです。入試、勉強などについてのお役立ち情報や、進路に関する最新情報、また高校生ならではのトレンドを取材した記事をアップしています。
ウェブサイト: http://shingakunet.com/journal/
TwitterID: studysapuri_shi
- ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
- 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。