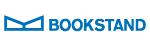人を殺さない元暗殺者の闘い〜ロブ・ハート『暗殺依存症』

暴力は身を焼き尽くす炎のようなものだ。
その危険な魅力を描いたことで注目される存在になったのが、第二長篇『黒き荒野の果て』(ハーパーBOOKS)が翻訳されて以来、ミステリー読者の間で人気が鰻上りになっているS・A・コスビーである。力を行使することは耐えがたい誘惑であることをコスビーは書いた。そして、同じ主題に踏み込んだ作家がもう一人現れた。『暗殺依存症』(ハヤカワ・ミステリ)のロブ・ハートである。依存症、依存症って書いちゃったぞ。
現在と過去を忙しく往復し、何が起きているかという情報を切れ切れに伝えることで読者の興味を惹くという叙述技法が用いられている小説である。最初に置かれているのは現在の叙述だ。主人公の〈私〉が、どこかの室内で自分を狙ってきた殺し屋に遭遇する場面から物語は始まる。そこはどうやら、先ほどまで何かのミーティングが行われていたようなのである。殺し屋と〈私〉はナイフの奪い合いになる。死闘の果てに〈私〉は自分の左脇腹から刃物の柄が突き出ていることに気づく。そして呟くのである。「ああ、よかった」と。
え、間違いじゃないのか。ナイフはあなたに突き刺さっているんですけど。殺し屋はぴんぴんしていて、あなたが大事にしているらしいノートを奪って逃げていってしまったんですけど。読者はそう思うはずだ。
謎は第二章で解かれる。「その日の数時間まえ」であることが明かされた叙述の中で、〈私〉がマークと呼ばれていること、P・キティという名の猫と二人暮らしであること、ケンジという日本人男性が彼のスポンサーであること、が明かされる。
スポンサーとは何か。そのすぐ後で前述のミーティング場面が描かれる。会に参加したケンジの第一声は「アサシンズ・アノニマスへようこそ」「私はケンジ。人殺しだ」である。
酒の問題を抱えている人のための自助団体「アルコール・アノニマス」の名を聞いたことがある人も多いだろう。略して「AA」と同じ頭文字を「アサシンズ・アノニマス」も持っている。会合のルールや、そこに集まった人々が唱えて心に刻み込むことになっている「十二のステップ」などは、本家「AA」に倣ったものになっている。要するにこれは暗殺依存症、つまり職業殺人者として依頼を請け負い、力を行使することに慣れ親しんでしまった者たちが、人生をやり直すための集まりなのである。ミーティングのリーダーであるケンジと〈私〉は、依存症から抜け出すための助言者(スポンサー)と被助言者(スポンシー)の関係にある。
〈私〉がどのようにして暗殺者になったか、そしてなぜ人を殺すのを止めようと思うに至ったかという個人史は、過去パートで時間軸をシャッフルした形で語られていく。これは書いてしまっていいだろうと思うが、〈私〉はかつて「青白い馬(ペイル・ホース)」と呼ばれた伝説の殺し屋だったのである。その名を聞くと、どんな猛者でも青ざめ、跪いて慈悲を乞うほどに恐れられている。その恐怖の殺し屋がなぜ自分のアイデンティティを捨てるつもりになったのか、ということが物語を牽引していく謎になっている。
さしあたっての課題は、〈私〉を狙ってきたロシア人らしき殺し屋が何者で、なんのために彼を狙っているか、ということだ。身を護るために〈私〉はそれを突き止め、闘わなければならない。ただし、相手を殺さずに。もうちょっとで誰も殺さずに一年を送ることができたという記念メダルをケンジからもらえるところなのだ。相手は殺しに来るが自分は殺せない、殺したくない、というハンデが物語に緊迫感を与える。主人公を魅力的に見せたかったら、何よりもまずハンデを持たせること。引き算の鉄則が守られた結果、読者は主人公の動向を知りたくて仕方ない気持ちにさせられる。
あれこれあって、まずは逃亡が始まる。ここで単独行ではなく、アストリッドというの女性とP・キティの三人旅になるのが上手いところである。アストリッドは闇医者で、〈私〉の治療もしてくれた相手なのだ。当然ながら危機が降りかかってくるが、アストリッドは、私は守られなければならない女ではない、と気遣う私に言い返す。単なるお荷物キャラクターとして女性を扱わない点も現代的でいい。
過去パートでは〈私〉の引き受けた殺人任務が、現代パートでは殺さない格闘が、それぞれディテール豊かに描写される。闘いに出かけるときに〈私〉はフェルトペンを手にするのだが、それは後段でちゃんと生かされる。小道具の使い方に無駄がないのである。そして、脇役たちの使い方もこなれている。〈私〉は闇夜をさまよっているようなもので、誰が信用できて誰ができないかがまったくわからない。自分を陥れようとしている者は誰か、背後にある企みは何かということは、行動し、傷ついて初めて判るのである。その中で意外な人物が敵であることがわかったり、味方についてくれたりする。さまざまな先行作を参考にし、それらが読者、観衆に与えているであろう先入観を逆手に取っているようなものだ。作中ではさまざまな映画についての言及がある。最も気に入っている殺し屋は誰か、と聞かれて〈私〉が映画「コンドル」の登場人物だ、と答えるのが渋い。ジェイムズ・グレイディ『コンドルの六日間』(角川書店)の映画化作品である。
作中にはさまざまなコードネームを持つ殺し屋たちが登場する。「知らぬ顔の半兵衛」とか「念仏の鉄」といったアンチヒーローが活躍する〈必殺〉シリーズの如し。〈必殺〉は大好きなのだけど、あれが現実だったらいろいろ問題があるだろう。どんな悪党だろうと人を殺していいものだろうかという問いがあって当然だし、殺しに手を染めてしまったらその悪人と同じ穴のむじなになってしまうではないか。〈必殺〉は当然発せられるべき疑問点を作劇でうまく回避した作品だ。『暗殺依存症』はその問いに正面から向き合ったとも言える。殺しちまったらおしめえよ、とロブ・ハートは書くのである。いや、おしめえよ、とは書かないが。
物語中に、「世界を変えるとかいうばかげたことを」言う悪人が登場する。〈私〉はその人物を単に「カネにものを言わせて、ゲームに割りこんできた」「ほかのクソ野郎たちと同じだ」と看破するのである。このくだりを読んで、誰とは言わないが実在のある人物を私は想起した。誰とは言わないが、SNSを買収して、世論さえも金で動かそうとし、ぼくのかんがえるさいきょうのあめりかを作ろうとしているあの人だ。いーろ、いや異論があれば甘んじて受けるが、たぶん想像は当たっているのではないだろうか。作品が発表されたのは2024年だし。
(杉江松恋)
- ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
- 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。