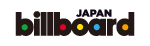<ライブレポート>Kroi、初のアリーナワンマンでみえた「新機軸」 新章開幕を叫び続ける5人の声
あらゆる音楽ジャンルを攪拌し昇華し続ける5人組バンド・Kroiが2月1日、昨年から続くツアーのファイナル公演【Kroi Live Tour 2024-2025 “Unspoil” at PIA ARENA MM】を行った。バンド最大規模のライブの舞台は、神奈川・ぴあアリーナMM。2月3日の結成7周年を前に、その節目を自分たちの最高の演奏で祝福した。
冒頭は暗いステージでスリリングなセッションが展開され、2分ほどバンドのジャムが続く。フロントマンの内田怜央(Vo.)がギターをかき鳴らすと、シームレスに「HORN」に移行。フロアが温まった中盤以降に演奏されることも多いこの曲が一発目に持ってこられたのも驚きだが、それ以上のサプライズはライティングや映像などのビジュアル演出である。冒頭の暗くてシックな雰囲気が3曲の間しばらく続いた。
これまでのKroiのライブでは極彩色の照明が使われ、極めてカラフルな世界観が組まれることが多かった。2023年1月の東京・LINE CUBE SHIBUYA公演などを振り返ってもサイケデリックなライティングが採用されていた。特に「HORN」は先述の通りパーティーソング的な側面があるので、以前ならばカラフルな演出が考案されていたのではないだろうか。後のステージMCで関将典(Ba.)が「今日の俺たち、ちょっとカッコイイんじゃない?」と言っていたが、冒頭の3曲にそれが具体的に現れていたのではないだろうか。実際、すこぶるクールだった。続く「Psychokinesis」、「Network」でもメンバーの表情がほとんど視認できず、さながらオランダ・アムステルダムで見たテクノパーティーのようなニュアンスだった。
「Network」で長谷部悠生(Gt.)のギターソロがあったが、そのシーンですら彼のプレイを強調する演出はなかった。明らかに新機軸。昨年1月の武道館公演以降、今回のツアータイトルにもサンプリングされている最新アルバム『Unspoiled』(2024年6月リリース)を含め、彼らは新章開幕を宣言し続けている。
もちろんこれまで連綿と紡いできたKroiの文脈を捨て去ったわけではなく、「Balmy Life」では一気に彼らのサイケデリックが爆発する。そこからはあっという間に彼らの“ホーム”だ。色鮮やかな照明にヒッピーアートを思わせるスクリーンの映像。アムステルダムの次は60年代のアメリカに飛ばされ、オーディエンスは享楽的なバイブスに包まれる。
益田英知(Dr.)のドラムフィルが印象的な「Green Flash」の後、彼の見せ場がやってくる。その後の「Monster Play」の終盤、彼が内田によってステージ前方へ招かれると、“ギターソロ”を万人のオーディエンスの前でプレイ。御大ジョニー・ウィンター(2014年7月逝去)への愛を叫んだ。「俺は学生の頃からブルースが好きだ。だけど周りにブルースを聴く友達なんていなかった。憧れのギタリスト、ジョニー・ウィンターに惚れてからは、ジョニーの愛機『Firebird』を弾く日々。このアリーナでギタリストとしてソロを弾くことができて俺は本当に幸せだ」
余談だが、筆者は御大の最後の来日公演(2014年4月)に足を運んだ経験がある。その数か月後に亡くなることを考えると、このときすでに満身創痍だったのだろうと思う。それでも、当時噂に聞くほどのヨボヨボ感はなく、魂が震えるような演奏を徹底していた。ともすれば“ミクスチャー”は、それぞれのルーツを単一に見ることを妨げる可能性もある。しかしこの日の益田の情熱は、往年のブルース・ギタリストへまっすぐ向けられており、誰もがその熱量に感化されたはずだ。御大も草葉の陰から喜んでいることだろう。「Monster Play」に続く「明滅」のイントロが、益田の想いに応えるように優しかった。
「Monster Play」にはもういくつか強調しておきたいことがある。バンドの初期から彼らを支えているこの曲は、会場をスケールアップさせるごとに規模感を増してきた。今回は『STRUCTURE DECK』(2021年1月リリース)に収録されている「Finch」のエスニックなチャントが添えられ、さながら“セルフサンプリング”のような印象を受けた。
彼らのミクスチャーな感覚は、いよいよ自分たちにも向けられているようだ。彼らのディスコグラフィーの中でもシンガロングを促しやすい曲で、当日もオーディエンスを巻き込んでいたが、その波紋は内外に広がり続けている。
ライブの中盤で演奏された「Shincha」は、先の武道館公演で本編の最後を飾った曲だ。そのときは決意表明的でエモーショナルな質感を伴っていたが、この日はより洗練されたニュアンスで披露された。The Isley Brothersの「Footsteps in the Dark, Pts. 1 & 2」に触れながら、千葉大樹(Key.)のピアノが流麗なメロディを奏でる。その場を即座にBLUE NOTEのようなオーセンティックな空間に変えられるのも、彼らの凄みのひとつだろう。その後のジャムセッションから「帰路」に至るまで、この時間帯は意図的にジャジーなセクションとして構築されていたように感じる。
本編も終盤に差し掛かると、エッジの効いたキラーチューンが大挙して押し寄せる。内田が「仕事終わりに小さいライブハウスに出てたような人たちがアリーナに立ってる。すげえ面白いことが起きてるんですよ」と語り、ファンへの感謝を伝えた。そのあと、関のベースリフが印象的なボサノヴァアレンジの「侵攻」が披露され、躍動感溢れる「selva」へ。それまでにも関と長谷部のソロパートは何度かあったが、改めてここで内田がベースとギターをコール。当代屈指の技巧派プレーヤー2人が激しい掛け合いをみせ、ほかのメンバーもしっかり支えた。
そしてこの日、「Hyper」の“答え”をみたような気がした。90年代のオルタナティブ(グランジ)・ロックのような趣と迫力で始まるこの曲は、聴き進めるうちに大きく印象が変わってゆく。それはまるで、この日のKroiそのものにも感じられた。赤い照明からどんどん色が足され、光るキューブがスクリーンに映し出されると、一気に拡散。ライブ冒頭のシックな雰囲気から爆散するように世界観を展開する今日のパフォーマンスを、1曲で踏破してしまうような気迫があった。「Hyper」はこれまでの公演でも披露されていたが、この日のビジュアルチームの汗と涙により、ついに完全体となったのではないか。
本編最後を飾るのは、Kroiの永久名誉必殺技「Fire Brain」。あえてこう書く理由は、この曲が記念すべき武道館ライブでは一発目に置かれていたからだ。あの日はライブのトリの役割を再三託していたこのキラーチューンに、それまでとは違うタスクを与えていた。それを新機軸が見えた今回のアリーナワンマンで、再びラストに持ってきたのである。「Finch」を掛け合わせた「Monster Play」にも言えるが、過去の傑作に対し解釈を変えることで前に進むヒントを得られることを、彼らは教えてくれる。
アンコールはたっぷり3曲。新曲「トレンド」に続き、「Jewel」と「Juden」が披露された。ここまでド級の映像を展開してきたビジュアルチームは、ハンドカメラでステージのメンバーを映し出す。時には長回しまで駆使しながら、緊張感のあるバンドの姿を紡いでゆく。極めて優秀なKroiのビジュアルチームは過去のライブを振り返っても出色のクオリティを担保していたが、それを踏まえても今回はレベルが違ったように感じられる。
正真正銘ラストチューンの「Juden」では、アウトロと共にエンドロールが映し出された。バンドのライブを体験したときの高揚感に加え、何か素晴らしい映画を見終わったあとの余韻が胸でうごめいていた。
なおKroiは、終幕後に2026年1月11日に大阪・大阪城ホール、同月23日に東京・国立代々木競技場第一体育館で初のアリーナツアーを行うことを発表している。
Text by 川崎ゆうき
Photo by Daiki Miura、Kaito Ono
◎公演情報
【Kroi Live Tour 2024-2025 “Unspoil” at PIA ARENA MM】
2025年2月1日(土)神奈川・ぴあアリーナMM
<セットリスト>
01. HORN
02. Psychokinesis
03. Network
04. Balmy Life
05. dart
06. Green Flash
07. Monster Play
08. 明滅
09. sanso
10. Pass Out
11. Shincha
12. ぴあアリJAM
13. 帰路
14. 侵攻
15. selva
16. Sesame
17. Amber
18. Hyper
19. Fire Brain
EN01.トレンド
EN02. Jewel
EN03. Juden
関連記事リンク(外部サイト)
Kroi、2026年1月に初のアリーナツアー
Kroi、ドラマ『オクラ』主題歌「Jewel」ライブ映像を公開
Kroi、反町隆史&杉野遥亮らキャスト陣と記念写真 主題歌担当の火9ドラマ『オクラ』撮影現場を訪問
国内唯一の総合シングルチャート“JAPAN HOT100”を発表。国内外のオリジナルエンタメニュースやアーティストインタビューをお届け中!
ウェブサイト: http://www.billboard-japan.com/
- ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
- 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。