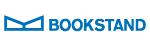なぜ私たちは「推す」のか? “虚構”の正体が浮かびあがるアイドル論の決定版

自分の好きなものを指すときに使われる「推し」という言葉。2021年新語・流行語大賞にノミネートされた、好きなものを応援する活動を表した言葉「推し活」も社会に浸透している。
「推す」という生き方を貫き、アイドルを40年以上語り続けてきた評論家・中森明夫氏の著書『推す力 人生をかけたアイドル論』(集英社)。日本で最初のアイドル誕生から現代に至るまで、時代とともに移り変わるアイドルについて徹底的に論究された一冊だ。
「『推し』という言葉を耳にするようになって、ハタと気づいた。ああ、そうか、自分はずっと『推し』ていたんだな、と」(同書より)
著者である中森氏は、それぞれ自分が好きなものを追いかけるという意味の「推す力」はずいぶん前から存在していたという。実際、1970年代に日本にアイドルが誕生してから歴代のアイドルたちは、確実に各時代に影響を与えてきた。
中森氏が「長い歴史の中で最重要の人物」と挙げるのが松田聖子さん。彼女が与えたインパクトは絶大で、街の女の子たちはこぞって「聖子ちゃんカット」にした。彼女が『赤いスイートピー』を歌えば、多くの人が花屋へと向かった。もともと赤いスイートピーは存在しなかったが、歌のヒットによって品種改良が重ねられて今では実在する花になった。1人のアイドルが新たな花を生み出したのだ。
さらにもう1人、伝説とも言われるアイドルが山口百恵さんだ。日本武道館でのファイナルコンサートで『さよならの向う側』を歌い、ステージにマイクを置いて去った話は語り草になっている。その後、家庭に入り、一度も芸能界に復帰していない。
「山口百恵に何ごとかを託した同時代の若い女子たちは、圧倒的に共感する。自分は一人の普通の女の子で、やがて平凡な主婦になるだろう。しかし、それはあの大スター・山口百恵が華やかな芸能界を捨て去って、手に入れたのと同じものなのだ」(同書より)
長年アイドルを見てきた中森氏は「アイドルは時代の反映ではない。時代こそがアイドルを模倣する」と語る。
その後、現代のアイドル業界は大きく変化した。かつてアイドルのメインステージだったテレビの影響力は低下し、新たな主戦場はライブとインターネットになった。牽引したのは「会いに行けるアイドル」をキャッチフレーズとしたAKB48。秋葉原の専用劇場で毎日ライブを行い、握手会ではファンが「推し」との触れ合いを楽しんだ。そして、インターネットの普及により24時間世界中に発信が可能に。アイドルをめぐるメディア環境は様変わりしたのだ。
またAKB48などのアイドルグループは、ライブ空間の使い方にも変化をもたらした。通常アイドルとファンはステージと客席で向かい合い、ファンに対して呼びかける恋の歌を歌うのがセオリーだ。対して48グループや坂道系の曲は、一人称が「僕」や「僕ら」。中森氏は、ステージで歌うアイドルが「僕」の一人称であることで、客席のファンと一体化しているという。
AKB48の大島優子さんが、2010年の第2回選抜総選挙でトップになった際に「(私に)ついてきてください」と話した。アイドルとファンは同じ方向を向いていることを象徴するようなシーンであった。
中森氏は週刊誌を賑わせたアイドルについても言及し、第五章で「加護亜依は勝慎太郎である」と書いた。加護亜依さんといえば12歳でモーニング娘。に加入し人気を博したが、未成年喫煙騒動で芸能活動を休止した過去がある。
「ロリータ的な可憐なルックスと、あまりにもアンバランスなスキャンダル。お騒がせアイドルのイメージがすっかり定着した。
勝新太郎は私生活はめちゃめちゃだけど、芝居をやると天才役者と讃えられた。いわゆる”役者馬鹿”である」(同書より)
中森氏が実際に加護さんに会った際も、煙草を吸いながらも相変わらずキュートだったという。彼女は、プライベートは破天荒だが、プリティーの天才なのだ。中森氏は、見かけは可憐だけれど中身は勝慎太郎氏や太宰 治氏のようでさえもある彼女を「無頼派アイドル」と例えた。
同書には数々の歴代アイドルたちが登場するが、中森氏はどのアイドルにもリスペクトをもって論評している。幼少期にアイドルに魅せられ、ライターとして魅力を伝え続けてきた中森氏は、アイドルというジャンルそのものを「推し」ているのだ。著者の人生をかけたアイドル論を読み、「推し」を力に変えて人生に彩りをもたらしてほしい。
- ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
- 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。