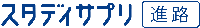推薦入試にも一般入試にも実は大事な定期テスト。しっかり高得点を取るコツは?
推薦入試を考えている高校生にとっては、学校の定期テストでしっかり高得点を取り、評定平均を上げることは当然重要。
それだけでなく、普段の授業をしっかり受けて定期テストで結果を出すことは、実は一般入試の成果にもつながってくる。
そんな定期テストの重要性や、高得点を取るためのコツについて、カンザキメソッド代表の神崎史彦先生に解説してもらおう!
【今回教えてくれたのは…】
 神崎史彦先生
神崎史彦先生
AO・推薦入試対策ゼミ・カンザキメソッド代表。
東進ハイスクール講師。
全国各地の高校や大学にて(年間60校以上)、志望理由書・自己推薦書・小論文・面接対策の講義・講演を担当し、延べ5万人以上が聴講。
『ゼロから1カ月で受かる 小論文のルールブック』『同 面接のルールブック』『カンザキメソッドで決める!志望理由書のルール【文系編】』『同【理系編】』など著書多数。
定期テストってやっぱり大事なの?
推薦入試を目指す人はもちろん、一般入試組にも土台作りとして重要

定期テストってやっぱり大事!推薦入試を目指す人はもちろん、一般入試組にも土台作りとして重要
大学・短大を推薦入試で受験しようと考えている人にとっては、評定平均に大きく影響する定期テストが大切なのは言うまでもないところ。
評定平均は、高校1年から3年の1学期までの全科目の成績を総合して算出されるので、それまでは定期テストで気を抜くことはできない(もちろん3年の2学期以降は気を抜いていいというわけではありません!)。
さらに、奨学金に申し込む際にも一定の評定平均が求められるため、予定がある人は、定期テストでしっかり結果を出し続けることが必要だ。
では、評定平均が関係ない一般入試で受験するつもりで、奨学金も関係ないなら真剣に取り組まなくてもいいかというと、決してそんなことはないと神崎先生。
「センター試験もそうですが、大学入試というのは高校までに学習する内容が基本となっています。
もちろん、普段の授業ではやらないようなレベルの難問が出題されたり、大学入試独特の解法テクニックが要求されたりする部分はあります。
ただ、そういった入試問題に取り組むうえでも土台となるのは高校の勉強。
土台がしっかりできていない人が、予備校で受験テクニックだけ学んでもレベルアップは望みにくいんです」(神崎先生、以下同)
その証拠に、一般入試で難関大学に合格する受験生は、当然のように学校の成績もいいことが多いのだという。
普段の授業で基礎をしっかり固めている人は、応用も身につきやすいからだ。
せっかく高校の授業で土台作りができるのだから、それを無駄にすることのないよう、一般入試が目標でも定期テストにはしっかり力を入れよう。
効果的な定期テスト対策とは?
大切なのは日頃の予習・復習。

短期的に一気にまとめて勉強するのはNG!?
試験前2週間で一気にやるのは非効率的
「定期テスト対策は試験の2週間くらい前から一気にまとめて!」という人も多いのでは?しかし、実はこの方法は非効率的だと神崎先生。
そのヒントになるのが下の「エヒングハウスの忘却曲線」。
科学的な研究に基づいた理論で、要は、人は何かを覚えても、20分後には4割以上、1時間後には5割以上、1日後には7割以上忘れてしまうというのだ。
 「定期テストというのは1カ月半から2カ月の間に勉強した範囲を対象に行われます。
「定期テストというのは1カ月半から2カ月の間に勉強した範囲を対象に行われます。
つまり、試験の2週間前では、試験範囲の多くを8割方忘れている状態で勉強を始めることになるわけです。
授業で覚えたことをいったん忘れて、それをもう一度まとめてやり直すというのはどう考えても効率が悪いですよね。
大切なのは授業で覚えたことをそのときにしっかり記憶に定着させることなんです。
だから、王道のアドバイスになりますが、当日、3日後、1週間後などに繰り返し復習することが、最も効率的な定期テスト対策です。
忘却曲線はやった分だけ緩やかになっていきます。
忘れないうちにやることを習慣づければ、1回の復習にそれほど時間もかかりませんよ」
また、授業はただ漠然と聞いているより、予習をして、概要を理解したうえで「わからないところ」を明確にして臨んだほうがベター。
疑問をもって先生の話を聞き、「なるほどそういうことか!」と納得できると頭に入りやすいからだ。
そうなると、忘却曲線はもっと緩やかになるので、勉強にかける時間はより省略できる。
面倒に感じても、毎日の予習をしっかりやるのがオススメだ。
「部活や友達付き合いもあって予習・復習の時間を作るのが大変だという高校生もいるかもしれませんが、成績のいい生徒というのは、スキマ時間をうまく使っていることが多いんですよね。
例えば、休み時間にさっと次の授業の予習をしたり、寝る前にその日の授業でやったことをさっと復習したりしています。
効率よく定期テスト対策をしたいなら、ぜひマネしてみましょう」
定期テストで高得点を取るコツってあるの?
しっかり点数を取るためのポイントは「ノートの取り方」にあり!

ノートをきれいにとることだけに集中してない!?
定期テスト対策として大切なのは「普段の授業を上手に記録すること」だと神崎先生。
つまりノートの取り方がポイントだということ。
しかし、先生が板書した内容を丸写しするだけではダメだという。
「先生は授業中、黙って板書だけしているわけではありません。
黒板に書いていないこともいろいろと話しているはず。
実はそこをしっかりと聞いて、ポイントをメモしておくことが大切なんです。
例えば、ある項目に関して、先生が板書した内容以上に詳しく説明したり、事例を挙げて理解を促したりしているなら、そこが試験に出る重要なポイントである可能性は高いですよね。
先生はちゃんとサインを送ってくれているんです。
ただし、板書せず、口頭で話すだけの内容は、聞いているだけでは忘れてしまいやすい。
だからメモが必須なんです。
また、先生の話から自分が気づいたこと、気になったことなどもメモしておくといいですよ」
授業中、つい板書に夢中になって、先生の話をあまりしっかり聞けていないなんてことはないだろうか? それではいくらきれいにノートが書けていても本末転倒。
ノートを見返しても授業の内容がいまひとつ思い出せないなんてことにもなりがちだ。
それに対して、先生の話の内容もしっかりメモするつもりで授業を聞いていると、理解度がそもそも違ってくる。
「あ、これは大事な話だ」「ここはポイントなんだな」と考えながら聞くことができるからだ。
もちろん、メモがしっかり取れていれば復習するときにも授業中の記憶をより鮮明に思い出せる。
試験に出る重要ポイントがしっかり押さえられて、日々の復習の効率も上がるのだから、定期テスト対策としては、非常に有効な方法なのだ。
定期テストの結果はどこまで気にするべき?
大事なのは点数や順位以上に自分の弱点を理解すること

テストの結果だけを見てよろこんだり落ち込んだりしてるのはNG!
定期テストの点数や学年順位は誰でも気になってしまうもの。
「前回のテストより数学の点数が5点上がった!」「今回は学年の上位50人に入れなかった…」と定期テストが終わるたびに一喜一憂している高校生も多いはずだ。
もちろん気になってしまうのは仕方がないところだが、結果だけを見てよろこんだり落ち込んだりしているだけではあまり建設的とはいえない。
気にしたほうがいいポイントはもっとほかにあるからだ。 「定期テストは何のためにあるのかをよく考えてみましょう。
その1カ月半から2カ月の間に授業で学んだことがどれだけ理解できているかを確認するために行われるテストですから、先生も大事なポイントを網羅的に出題します。
つまり、どこに自分の穴があるのかをみつけるいい機会なんです。
だから、点数そのものよりも、どの問題ができなかったのか、どの項目の理解が足りなかったのかを、しっかり振り返ることが大切。
弱点がわかれば、そこを埋めるための勉強につなげることができますから」
このように定期テストの結果から、そのつど穴をみつけて埋めていくことができれば、大学入試に向けた土台作りとしても非常に有効だ。
なお、点数を気にするのなら、平均点と比べないとあまり意味がない。
問題を作る先生次第で試験の難易度は大きく変動しやすいからだ。
また、学年順位の変動についてもありがちなパターンがあると神崎先生。 「よく3年になって順位が下がる生徒がいますが、3年になると受験に向けて本腰を入れる生徒が多いので、周りが伸びている分、順位が下がるのです。
自分の学力が急に落ちているわけではないので、そこからエンジンをかければ、順位をもち直すことは十分可能ですよ」
一夜漬けでも定期テストで高得点は取れる?
直前対策だけで点を取れる人もいるが、実はそれこそ一番危険なパターン!

一夜漬けで叩き込んだ知識は試験が終わればすぐに忘れる
暗記が得意で、普段の授業はまともに聞いていないのに、試験直前に教科書を読み込んで定期テストで高得点をとってしまう人は確かにいるもの。
そんな同級生を見ていると、「日々マジメに勉強しているのがバカバカしくなってくる…」と感じてしまうこともあるかもしれない。
しかし、神崎先生によれば、この「一夜漬けで高得点」を繰り返している生徒が、一般入試で大学を受験する場合には、最も危険なパターンなのだとか。 「先ほどの忘却曲線を思い出してください。
一夜漬けで叩き込んだ知識は試験が終わればすぐに忘れていきます。
つまり、『一夜漬けで高得点』パターンの人は、知識の積み重ねができていないんです。
しかし、模試や本番の入試では、当然ながら一夜漬けなどできません。
学校の成績はずっといいのに、3年になって模試を受けるとボロボロで、本番の入試もダメという生徒は意外と多いですね」
目先の定期テストだけを一夜漬けでクリアしても、入試で通用する学力は鍛えられない。
そのことはくれぐれも肝に銘じておこう!
***
★ほかの記事もCHECK!
集中しやすい?集中しにくい?“ながら勉強”って実際どうなの?
現役東大生&東大卒業生113人に聞く!効果的な一夜漬けの方法とは?
小論文完全マニュアル① 意外とみんなわかってない!?目からウロコの「小論文とは?」
英語で自己紹介する人必見!「部活で頑張ったこと」を英訳&解説
推薦・AO入試を受験するなら必見!面接のNG&OK回答例
投稿推薦入試にも一般入試にも実は大事な定期テスト。しっかり高得点を取るコツは?は【スタディサプリ進路】高校生に関するニュースを配信の最初に登場しました。
関連記事リンク(外部サイト)
やりたいことが変わった!というときに知っておきたい「大学編入」
AO入試って?推薦入試や一般入試と何が違うの?
青春を無駄にするな!眠気を覚ます方法とは
進学や高校生に関するニュースやトピックスを配信する記事サイトです。入試、勉強などについてのお役立ち情報や、進路に関する最新情報、また高校生ならではのトレンドを取材した記事をアップしています。
ウェブサイト: http://shingakunet.com/journal/
TwitterID: studysapuri_shi
- ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
- 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。